以下、本文になります
渇望がもたらした突破力で映像の世界へ 〜「逆転しない正義」を託した注目の朝ドラを語る
Cross Talk 『志』その先へ-卒業生・修了生対談-

倉﨑 憲 氏
NHK チーフ・プロデューサー。2011年3月に同志社大学法学部法律学科卒業。学生時代にはラオスでの小学校設立や世界一周を成し遂げる。卒業後、NHKに入局。これまで連続テレビ小説「おかえりモネ」「エール」、大河ドラマ「いだてん」「平清盛」など、多数の番組制作を担当。2025年にはチーフプロデューサーとして連続テレビ小説「あんぱん」の制作に携わる。
飢えを満たすラオスの旅で「生きている心地」を実感
- 小 原
- 今回は、2011年3月に本学法学部法律学科を卒業された倉﨑憲さんとの対談です。倉﨑さんは学生時代にラオスでの小学校設立や世界一周を成し遂げられています。卒業後はNHKに入局し、これまで連続テレビ小説「おかえりモネ」「エール」、大河ドラマ「いだてん」「平清盛」など、多数の番組制作を担当してこられました。25年にはチーフプロデューサーとして連続テレビ小説「あんぱん」の制作に携わっておられます。早速ですが、学生時代のお話からお聞きしましょう。
- 倉 﨑
- とにかく飢えていて、もっといろんな事をしたいという感情が渦巻きながら大学1年生を迎えました。4つもの球技系サークルに入って大学生活を満喫しようとしましたが、それで上を目指すわけでもない。「自分は何をしているんだろう」と、コンプレックスの塊だったんですね。もっと「生きている心地」を感じたいという思いが爆発して、2年生になる前、初めての一人旅に出ました。選んだのはタイとラオスでした。
- 小 原
- 「飢えていた」というのは、素晴らしいことですね。倉﨑さんが学ばれた同志社香里高校は、公立の学校と比べるといろんな意味で自由があり、特徴的な教育を行っていると思います。それでも大学に入ったならば、今までできなかった事をしようという気持ちがあり、餓えを満たすために世界へ出ようと思われた。その初めての一人旅で、一番ご自身に衝撃を与えた出来事は何でしたか。
- 倉 﨑
- ラオスでは公共交通機関を使わず、自分の足で疲れるまで歩き回ろうと思っていました。持参したサッカーボールを持って学校を回ると、100人くらいの子どもたちが「うわーっ」と、ひたすらボールを追いかけるんですね。日本では感じたことのない「生きている心地」がしました。現地では奥地に行けば行くほど、学校がないんです。現地の方にインタビューをさせていただくと、一番欲しいのは学校だと。「自分の子どもには、少なくとも字の読み書きぐらいは学ばせてあげたい」と言うのです。メディアを通じて途上国の実態を知っていたつもりでしたが、生の声として受け取ったことで、帰りの飛行機の中で、何か自分にできる事はないかと考えました。そこで、ラオスに小学校を建てたいと思い立ってしまったんですね。帰国後、すぐに学生国際協力団体を立ち上げました。
- 小 原
- その感覚はすごく大事ですね。私たちは幼少期から大学まで勉強をして、世界や自分を知っていきますが、本当に腹の底から自分が生きた心地をするという経験をどれくらいしているでしょうか。教育の現場でもなかなかないと思います。そういう機会を本能的に求め、子どもたちとの交流の中で感触を得られたことが、その後の人生に大きな影響を与えていくのですね。帰国後、団体を立ち上げたということですが、もともと人をまとめる力をお持ちだったのですか。
- 倉 﨑
- 自分と似たような感覚を持つ学生がたくさんいることに気づいたんです。当時2007年頃は、今よりも国際協力団体が少なかったので、新しいチャレンジを一緒にしたいと思ってくれる学生が多かったんですね。同志社大学の良いところは、好奇心旺盛な学生が多いところ。だからこそ私の提案にも、次々に乗ってくれたのだと思います。
- 小 原
- そうして仲間を作り資金を集めて、最終的に学校を設立されたのですね。
- 倉 﨑
- はい。イベントを開催して150万円を集め、1年後に再度ラオスへ行きました。今度は教育省の方々とさまざまな村を回り、本当にその村に小学校が必要なのか、将来の子どもたちの人口推移はどうか、建設後も継続して運営できるのかと徹底的に調査しました。この、現地に行って生の声を聞く姿勢は、現在の私の仕事にも通じる現場主義の基礎となっています。ドキュメンタリーでもドラマ制作でも、取材がすべてですから。
- 小 原
- 教室では勉強できないような事を外で学んでこられたのですね。それが教室内での知識の吸収や知的交流と、うまく組み合わさると一番いいなと思います。
- 倉 﨑
- 法学部法律学科で学んだ事も、今につながっています。ドラマ制作をしていると弁護士や法廷のシーンが出てきたり、取材や交渉で法律の勉強が少なからず、考え方として生きていたりします。他にも選択科目の授業で配布されていた公募がきっかけで、ロサンゼルスを訪問する現地研修プログラムに参加しました。個性豊かな学友にも恵まれて、同志社にはいろんな機会がそこらじゅうにあることを感じました。
- 小 原
- その伝統を維持したいと思います。
- 倉 﨑
- 近くにもいろんな大学があり、交流しやすい環境も良かったです。稲盛財団の京都賞の学生スタッフも経験して、非常に勉強になりました。
- 小 原
- 今は若い人が少しおとなしくなったと、一般論としてはよく聞きます。もしそういう時代になっているとするならば、同志社はそういう潮流に抗うぐらい意気盛んで好奇心旺盛な学生が学び、世界に出ていけるような環境を作ることができればと強く思います。同志社大学は国際主義を重要な教育理念として掲げています。それは単に国際的な教養を身につけるということではなく、国際社会に通用するような感覚を持つ人を育てたいということです。150年前、同志社英学校が始まったとき、授業は基本的に全部英語でしたし、当時の最先端の国際感覚を身につけられる場でした。倉﨑さんは、その伝統のまさに体現者ですね。
映像の力に導かれて世界を目指す
- 倉 﨑
- 小学校を建てた後、関東の学生からメッセージが来ました。カンボジアに小学校を建てている団体の人で、「思いは同じ。一緒に本を出版しませんか」と。そこで私も写真担当として協力し、「僕たちは世界を変えることができない。」という本を自費出版しました。
- 小 原
- 一見、ネガティブに思えるタイトルですね。
- 倉 﨑
- その後にbutが続くんですね。「じゃあ、自分たちはどうする?」と。出版すると、たまたま映画プロデューサーの目に留まり、トントン拍子で、向井理さん主演で映画化されたんです。撮影現場に行かせてもらったとき、無名の一大学生たちの活動がこうして映像化され、多くの人々に観ていただけることに深く感動しました。映画を観た方々からは、「国際的な活動を私もやってみたいと思った」「毎日死にたかったけれど、もうちょっと生きようと思いました」というメッセージが届いたんです。そのとき初めて、映像の力ってすごいなと実感しました。この経験が今のNHKにつながっています。現実やドキュメンタリーには圧倒的な力があるとは思いますが、ときと場合によっては、フィクションの方がノンフィクションを超える力を人に与えられるんじゃないか。そう思って、今は生きています。
- 小 原
- 映像の力にハッとさせられたのは、いつ頃のご経験ですか。
- 倉 﨑
- 大学卒業前、4年生でした。半年休学して世界一周に行ったので、大学は4年半通いました。
- 小 原
- 世界一周で一番印象的だった事は何ですか。
- 倉 﨑
- アメリカとフランスで、映画の撮影現場を通りかかったことがありました。スタッフには白人もいれば黒人もいて、アジア人もいる。「アジア人でも世界で戦えるんだ」と初めて思いました。いつか自分も世界中のスタッフと一緒に、世界中の人々の心を揺さぶれるような作品をつくってみたいという志が芽生えた、今につながる原体験です。マーケットはもう世界にあるべきだと、視野を広げてくれた経験でした。
- 小 原
- 映像は国境を越える力を持っていると思います。日本の映画やドラマも、かなり世界に通用するようになってきましたね。
- 倉 﨑
- 数年前よりはだいぶ海外に届くようになってきたと思います。その国の言語で配信することが非常に重要だと感じます。以前、NHKからハリウッドに留学させてもらったことがありました。世界各国のプロデューサーやバイヤーが集まる地で、一番歯がゆかったのが「あなたが今まで手掛けた作品は、どこで観られるのか」という質問でした。私が関わったのは基本的に国内向けの日本語作品なので、英語字幕などもついておらず、すぐに差し出せるものがないんです。日本はまだまだ足りていないと痛感しました。今、私が制作統括している「あんぱん」は、朝ドラで初めて世界での直後配信にトライしています。海外に売り込むプロデューサーの存在も必要です。
- 小 原
- 「あんぱん」は日本固有のものを扱っている気はしますが、同時に非常に普遍的なテーマがあると思います。まさに世界に発信できる内容を備えている。それに字幕をつけたり、配信のタイミングをうまく図ったりすることによって、視聴者はどんどん広がるのですね。
- 倉 﨑
- 世界がマーケットだという意識を、制作者全員が持つべきだと思います。例えば「おしん」のような物語は、文化が違ったとしても万国共通で、世界に届く可能性がありますから。そういう普遍的なメッセージ性を持つドラマを、「あんぱん」を含めてつくっていきたいです。
- 小 原
- 「おしん」は世界のロングセラーです。日々の労苦や家族愛といったテーマには、国境を越えて普遍的なものがありますよね。宮﨑駿監督の作品にも、極めて日本的でありながら、外国の人でも深く共感するものがある。自分たちの思い込みというバリアを越えていく必要を、今までいろんな作品で感じてきました。その点で日本のコンテンツは世界に通用するのではと思います。
- 倉 﨑
- おっしゃる通りですね。日本の知的財産は海外での人気が非常に高い。これは映像業界だけでなく、京都や、そこにある同志社も含めて、日本が自信を持って世界に発信していくべきだと思います。漫画原作の権利一つをとっても、今や日本国内だけでなく、世界各国が争奪戦を繰り広げています。日本が負けてはいけないと感じます。

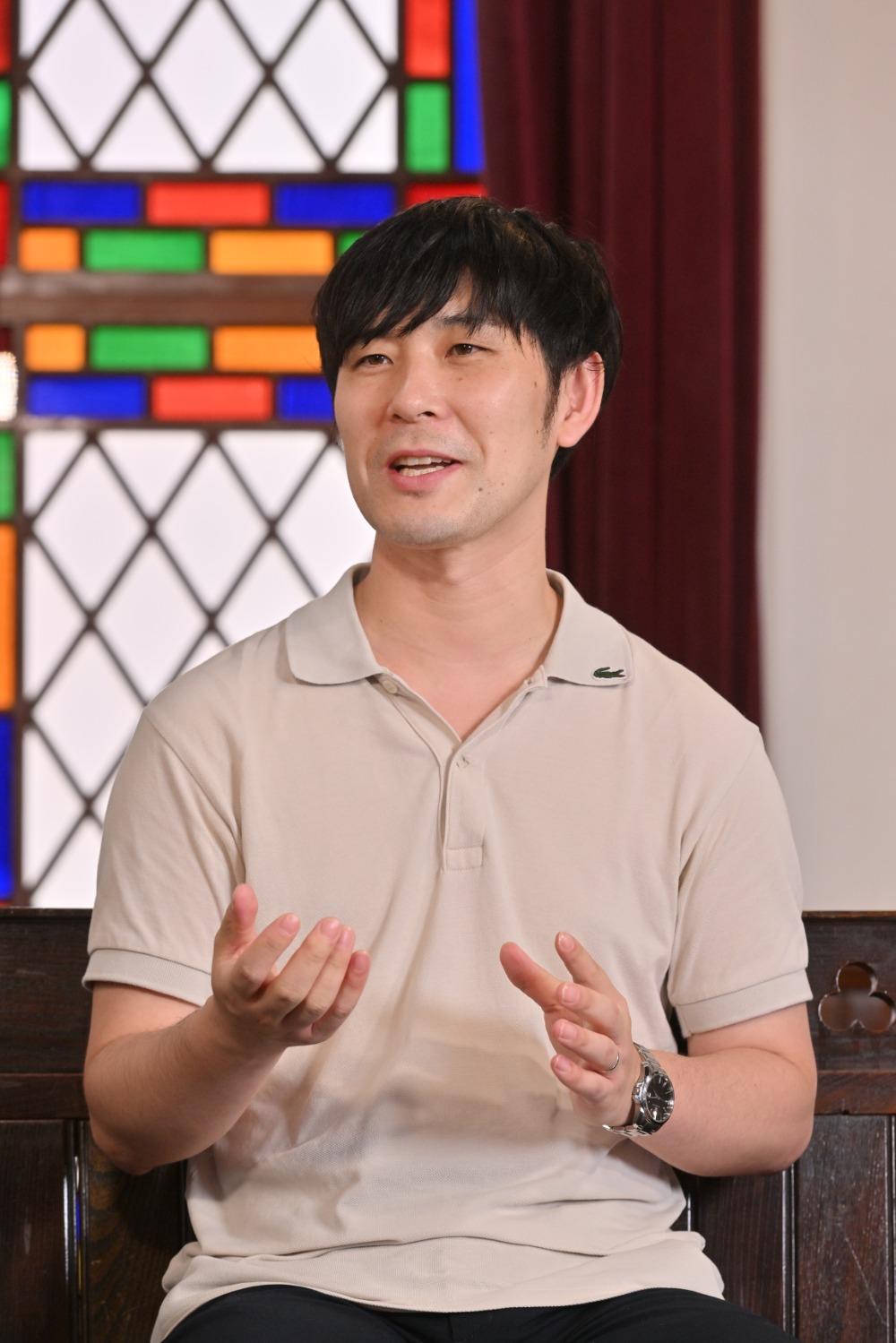
「あんぱん」に込めた「逆転しない正義」
- 小 原
- さて後半は、現在のお仕事のお話を伺いましょう。チーフプロデューサーとしてお忙しい日々と思いますが、監督とプロデューサーの役割の違いを教えてください。
- 倉 﨑
- レストランにたとえれば、オーナーがプロデューサーで、シェフが監督のようなものです。オーナーが店作りのコンセプトを考えて予算を引っ張ってきて、素晴らしいシェフたちを集めて最高の料理を作ってもらう。最終責任者がプロデューサーです。
- 小 原
- 「あんぱん」というテーマはどのように決まったのですか。
- 倉 﨑
- 2022年12月、上司から「放送100周年を迎える2025年、上半期の朝ドラの制作統括を担当しないか」と言われました。その帰り道から企画を考え始めました。その日は頭の整理も兼ねて雨に打たれつつ、武者震いしながら遠回りをして帰ったんです。ゼロから企画できる朝ドラでのチーフプロデューサーは初めてだったので、「何をやるべきか」と考えたとき、無意識にアンパンマンのマーチを口ずさんでいました。「なんのために 生まれて なにをして 生きるのか」「こたえられないなんて そんなのは いやだ!」と。なぜその歌詞が出てきたのかと考えると、正直、NHKを辞めようかと悩んでいた時期だったんです。小さい頃から聞いてきたアンパンマンのマーチの歌詞の深さに気づき、自分自身に問いかけられている気がしました。そのとき、自分はNHKを辞めて違う道に進むのではなく、朝ドラを全うしてヒットさせ、日本中、世界中の多くの人の心を揺さぶれるものをつくるべきだと、強く思いました。そのとき、やなせたかしさんという方に俄然、興味が湧いたんです。翌日からやなせさん関連の書籍を読み、もしかしたら朝ドラの題材になり得るんじゃないか、そして、やなせさんを引っ張ってきた奥さんの暢(のぶ)さんの存在がなければ、漫画家やなせたかしもアンパンマンも生まれなかったかもしれないと思ったとき、やなせ夫妻の半生を朝ドラで描きたいと思ったのが、企画の発端です。
- 小 原
- アンパンマンは勧善懲悪的なものにはまらず、要所要所で、そう単純ではない話が織り込まれているところが魅力だと思います。倉﨑さんはアンパンマンのどういうところに心惹かれますか。
- 倉 﨑
- アンパンマンは「逆転しない正義」を一番体現したキャラクターだと思っています。今の世の中は自分本位な方が増え、利他の精神が希薄になりつつある。そんな中で、自分が犠牲になっても、目の前にお腹を空かせている人がいればパンを差し出す。これこそが、本当に逆転しない正義だなと。やなせ先生の自伝を読むうちに、先生も戦地に行かれていたことを初めて知りました。そこで何よりも辛かったのが空腹で、その原体験が、アンパンマンが生まれるきっかけの一つになったと知りました。戦争とは、立場が変われば正義がいとも簡単に逆転する。これは国と国だけの話ではなく、個人と個人の間の話でもある。この「あんぱん」でも、そのことを描きたかった。そして、じゃあ「逆転しない正義」は何なのかという問いを、暢さんとたかしさんが二人でずっと探し続け、たどり着いた先がアンパンマンだったのだと思います。そこを丁寧に、心を込めて描いていきたいです。
- 小 原
- 確かに今の世界情勢を見ても、正義のあり方は簡単に変わっていきます。我々は何を基準にして生きたらいいかということも見失いがちですね。2025年は戦後80年です。その年にドラマの中で戦争の時代が描かれるのは、意味があると思います。
- 倉 﨑
- おっしゃる通りです。そんな年に、実際に戦地に行かれ、辛い経験をされたやなせさんを題材に朝ドラを制作できることは、自分の中で腑に落ちました。
「志」と、未来を拓く「人間力」と「突破力」
- 小 原
- 私たちは志の持ちよう一つでまったく違う人生を歩むこともできるし、今の日常を破って違う生き方を選び取ることもできる。志は本当に大事だと思います。倉﨑さんにとって志とは何ですか。
- 倉 﨑
- 世界中の人たちと一緒に、世界中の人々の感情を、ぐらんぐらんに揺さぶれるような作品を生み出し続けることです。
- 小 原
- ラオスでサッカーボールを蹴ったとき、生きた心地がしたというのは、まさに子どもたちとの交流の中で魂を揺さぶられたご経験でした。その後、映像によっても魂を揺さぶられ、今度は人々の魂を揺さぶりたいということですね。
- 倉 﨑
- 映像をつくる仕事の素晴らしい点は、まず取材も含めた制作段階で自分たちが心を揺さぶられることです。逆に、自分自身が心を揺さぶられないものからは、良いものは生まれない。キャスティングもセリフ一つをとっても、自分たちがまず感情を揺さぶられたものに対して正直になる。それは絶対に正解であり、後悔しません。それを脚本やセリフに落とし込み、自分が心震えた人にオファーし、さらに完成した作品を自分たちが見てもまた、心を揺さぶられる。それを世の中に届け、皆さんの心を動かすことができる。本当に幸せなことだと感じています。
- 小 原
- 倉﨑さんの高い志と、倉﨑さんご自身が、同志社のユニークな教育が生み出したお一人であることを痛感しました。倉﨑さんのような方がこれからも輩出されることを願いますが、これからの社会で求められる人物像について、どうお考えですか。
- 倉 﨑
- 一番大事なのは、コミュニケーション力を含めた「人間力」だと思います。もう一つは「突破力」。口先だけでなく、まずは自らの行動で見せていく力です。どんな状況や環境であっても、とにかく前に進む。「あんぱん」のヒロイン、のぶさん の突破力もすごいと思います。以前、とある役者さんに言われた言葉が心に残っています。「本当に素晴らしいプロデューサーとは、何が起こっても、ありえない絶望が起こったとしても、前に進み続ける人だ」と。
- 小 原
- 「突破力」という言葉は素晴らしいですね。「おしん」の話にも通じますが、世界の人々の魂を揺さぶる作品は、登場人物の突破力に強く共感するのだと思います。私たちは困難に直面したとき、それを越える力、つまり自分の中にある突破力に気づかされることがあります。新島襄自身も、当時の鎖国社会を突破して日本を飛び出していった人物でした。その良き伝統を私たちは引き継いでいきたいですね。最後に、これからの同志社大学への期待や、今いる学生さんに対するメッセージがありましたら、よろしくお願いします。
- 倉 﨑
- どの分野でもいいので、世界で活躍できる人材が、同志社からもっと輩出されてほしいなと思います。現役生には、やはりどんどん、どんどん失敗してほしい。どれだけ多くの、どれだけ大きな失敗をして、かつどれだけ成功体験を積み重ねてきたかが、世界を相手に勝負して勝っていけるかどうかの肝だと思います。学内外に限らず、挑戦を続けていただきたいです。チームビルディングも大事です。私自身も学生時代の国際協力団体での、ある種のチームリーダーとしての経験が今につながっています。学生時代にどれだけ多くの場数を踏めるかということだと思います。
- 小 原
- 社会に出てからもいろいろな経験をすると思いますが、失敗ができる時間として、大学時代は貴重ですね。
- 倉 﨑
- あとは旅をしてほしいです。今もう一度学生時代に戻れるなら、もっと長期間世界を回っていただろうと思います。時間を自分次第でいかようにも使えるのが、学生時代の良いところです。
- 小 原
- 今日は学生時代からお仕事の話まで、多岐にわたり本当にありがとうございました。倉﨑さんのような突破力を備えた人物が、同志社からますます出てくることを願っています。

| 関連情報 | 同志社大学公式YouTubeチャンネル 対談動画は上記リンクよりご覧ください。 |
|---|