“D”iscover -Campus-


「白血病」の治療薬開発に向け、新たな可能性を切り開く ~同志社大学 若き研究者の挑戦~(後編)
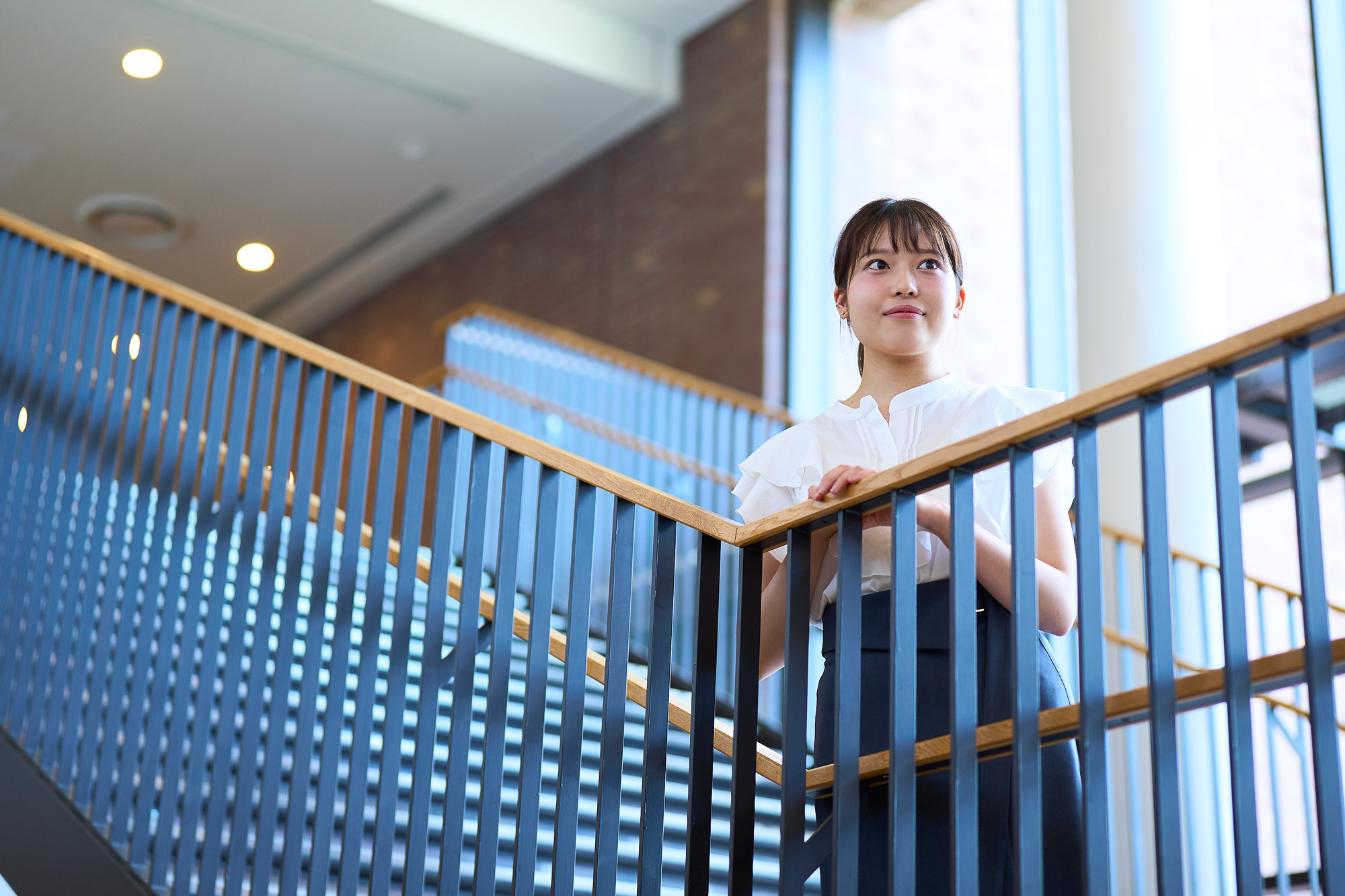
英語やキャリアなど、多彩な支援が研究を後押し

お金に関しては、支援していただくにあたって、研究計画の立案と使途の説明も求められています。どのような研究を行い、そのためにはどんな試薬が必要で、お金はどれぐらいかかるのかといった計画をしっかりと立てなければいけないのです。そういった経験は初めてでした。修士課程時代はどちらかと言えば場当たり的に、「こんなことがしたいです。そのためにはこんな試薬が必要です」と先生に相談し、準備をしてもらっていました。慣れないことなので苦労しましたが、資金を調達したり計画を立案したりすることは研究者として不可欠なスキルです。今では、プロジェクトを通して“一人前”の研究者になるための練習ができているんだと感じています。また、苦労して手にできたお金だからこそ、ムダにせずしっかりと成果につなげていこうという気持ちも強くなりました。
若手研究者が世界へ挑戦する後押しをすることもプロジェクトの目的の一つです。そのための具体的支援として、英語のトレーニングがあります。私の場合、論文を英語で執筆するためのスキルを身につける英語論文執筆ワークショップに参加しました。また、国際学会で発表することを想定し、英語によるプレゼンテーションを学ぶ英語アカデミックプレゼンテーション研修を受講しました。ここでは、質疑応答といった実践的な訓練も積むことができています。
博士課程に進むにあたっての大きな不安の一つが、修了後の進路です。修了するのは、どんなに早くても27歳。その頃に新卒で就職先があるのだろうか、大学や公的研究所などに残る道はあるのだろうかなど、不安は尽きません。そこでプロジェクトでは、キャリア支援の取り組みも行われています。私は博士後期課程1年次と2年次に、京都クオリアフォーラムが主催する「博士キャリアメッセKYOTO※」に参加しました。ここには様々な企業の方にお越しいただき、直接キャリアに関する話を聞かせてもらうことができました。企業の方の前で研究内容の発表をする機会も設けられており、研究に対するアドバイスをいただくこともできました。
プロジェクトは、文系・理系を問わずすべての研究科の学生を対象にしています。採択された学生が集まって研究内容の発表や交流を行う場も設けられています。私はそれまでに、他学部の人とほとんど接点がありませんでした。文系の方の研究内容や研究手法を聞くことは私にとって非常に新鮮で、視野が広がる体験でした。新しい刺激をもらい、自身の研究へのモチベーションを高めることができています。
今後の目標は、まずは2025年3月の国際学会への参加です。海外の研究者がどのような研究をしているのかを、肌で感じたいと思います。英語の講座で学んでいることを生かし、直接コミュニケーションして意見交換にもチャレンジしたいです。できることなら、学会で出会った外国人研究者と継続的にコンタクトし、情報交換できるような間柄になりたいです。博士課程を修了後は一旦アカデミアに残り、基礎研究を続けていきたいと考えています。
「やりきった」という自信を得て次のステップへ

同志社大学はとても研究しやすい環境だと感じています。実験機器は不足なく整備され、困ることはありません。先生方は厳しさと優しさを備えていて、温かく見守ってくれつつ疑問や不安には的確なアドバイスで応えてくれます。研究テーマの設定も基本的に学生本人の希望に沿って行われ、研究の進め方についても学生の意思に任せてもらえる部分が大きいです。自由な環境で学生の思いを尊重してくれ、なおかつ困ったときはいつでもサポートしてもらえるのが、同志社大学という研究環境だと思います。
すでにお話ししたとおり、私は学部生時代には博士課程に進むことを想像していませんでした。もちろん、高校時代もそうです。博士課程に進学し、研究に取り組むことには大変な側面もあります。しかし、同じぐらいおもしろさややりがいもあります。では、どうして私はこうやって研究に取り組んでいるのだろうと考えると、自信をつけたいからかもしれません。私はこだわりの強い性格のせいか、「あのときは◯◯すればよかったのかもしれない」「もっと◯◯できたはず」と、完璧を目指してしまうところがあります。そんな自分に対して、「この研究をやりきった」「これを見つけたのは私だ」と言い切りたくて研究に取り組んでいるような気がします。そんな動機で研究に取り組む大学院生がいることも、高校生をはじめとして研究者という道に興味がある人には知っておいてもらいたいです。
博士課程に進むべきかどうかを迷っている修士課程の学生や学部生、もっと言えば進路に迷うすべての人に対して、「目的や目標を見失わず、続けていたら何かの結果が出るものだよ」と伝えたいです。目の前のことで一喜一憂する必要はありません。諦めずに続けることはすごく意義のあることです。そこで得られるものは、必ずあるはずです。
※博士学生や企業関係者が博士に対する期待やキャリアについての現状を本音で語りあい、キャリアの選択肢を広げる場として、京都クオリアフォーラム・人材育成Gのもと、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)に採択された京都・奈良6大学が企画運営しています。