“D”iscover -Campus-


「ヒトに合う次世代の技術」を求め、脳科学研究 に挑む ~同志社大学 若き研究者の挑戦~(後編)

企業との出会いの場が充実。キャリアへの考えを深められる

「次世代研究者挑戦的研究プロジェクト(Spring! Doshisha)」については、研究室の先生から教えてもらいました。「様々な分野の相互理解力を涵養し、挑戦的・融合的な研究に専念するための機会を設ける」というプロジェクトの性質が、機械工学、医工学、脳科学を横断・融合して「よりヒトに合う技術の開発を」と考えている私にぴったりだと思い、応募することにしました。
採択されたことで様々なメリットを得られています。その1つが異分野交流です 。例えば「フューチャーデザイン演習」という、分野をまたいだ学生や社会人学生が共に学ぶ「協創」ワークショップ方式の演習科目に参加しました。未来視点に立ってどのような技術が今後生まれるか予測することをテーマに、私は化学工学系、情報工学系、生命科学系の学生、企業の現役技術者の方と一緒にディスカッションを行いました。また、合宿形式の異分野交流会にも参加しました。「災害に対する防災シナリオ」をテーマにしてグループワークが行われ、私は化学工学系、社会学系、スポーツ科学系の学生と一緒にディスカッションを行いました。これらの交流において、メンバーはそれぞれ専門分野が異なるため、出てくるアイデアもばらばらで、最初は「うまくまとまるのだろうか」と難しさも感じました。しかし、議論を重ねるうちにアイデアが育っていくという体験をすることができました。専門性が異なるからといって何も恐れる必要はなく、まずは自分の経験や考えを臆せずに発信してみることが大事だと学びました。
発信したことをもとにして、それぞれの足りない専門知識の埋め合わせが行われ、その中で新たな視点から議論が発展することもありました。このようにして異分野融合の源泉となる部分を体験することができました。きっと将来、同じような経験をすると思います。そのための有意義な準備になりました。

驚いたのが、企業とのつながりをうながす支援の手厚さです。プロジェクトが主催する企業見学、プロジェクトから紹介された企業への訪問 、プロジェクトに紹介してもらった博士向け就活セミナーへの参加による企業との出会い、さらに京都クオリアフォーラムが主催する「博士キャリアメッセ」での出会いなど、多彩なアプローチを通じて合計8社とつながりを持ち、企業が取り組む研究や技術について聞かせてもらったり、私自身の研究やビジョンについて話を聞いてもらったりする機会を持つことができました。それらの機会を通して、企業が博士課程修了者には自ら課題を設定する能力 やPDCAを回す力、複数の分野やそこに携わる研究者の知見を融合させて新しいものを生み出す力に期待していることを知りました。企業が求めているものを知ることは、研究活動においても「この取り組みは力を入れて頑張ろう」など、モチベーションにつながっています。
プロジェクトに採択されると、年額40万円の研究費や月額15万円の研究奨励費(生活費相当)などが支給されます。金銭的な支援をいただけることはもちろんありがたいのですが、それ以上に役に立っているのが、研究資金の管理に対するサポートです。研究資金である以上、「何に使うか」「どのように使ったか」などの申告や報告が必要です。使い道にルールがありますし、申告・報告の仕方にも決まりがあります。それらの事務的な作業は、研究者にとっては苦手な領域だと思います。しかし、研究を進めるうえで資金の調達や管理は避けて通ることなどできず、そこに付随する手続きなども「必須のスキル」と言えるものです。
ここで助かったのが、プロジェクトの事務局の方によるサポートです。ルールや手続きについてわからないことがあれば、気軽に相談することができました。いつもていねいに教えていただけたおかげで、手続きが滞ることもなかったです。この経験は、きっと企業や研究機関などに所属した際も役立つと思います。研究資金 について考えることは、研究の計画を緻密に考え、計画にのっとって研究を進めるということにもつながっています。研究計画の立案が疎かだと、資金の用途も事前の申告と異なるものになってしまうからです。これもまた、将来に役立つ経験が積めていると感じるポイントです。
ヒトに焦点が当たり、機械がヒトに歩み寄る技術が誕生する
当面の大きな目標は、今年10月にアメリカ・シカゴで開催される北米神経科学学会に参加することです。先生と相談し、参加の目的を2つ設定しました。1つは私が取り組んでいる研究に近しい位置にある、脳と運動に関する研究はどのようなものが行われているかを知ることです。ヒトであれマウスなどのげっ歯目であれ、関連する研究の動向をつかみたいです。
もう1つは脳活動をとらえるためにどのような手法が研究されているかという、情報をキャッチすることです。ヒトの脳活動をとらえるために、脳波の記録や近赤外線を用いた方法があり、低侵襲で活動を記録できます。一方でげっ歯目などにおいては私の研究で用いているカルシウムイメージングや電極を用いた方法があり、詳細な活動データを得ることができます。もしかすると、それぞれのメリットが組み合わさったような、低侵襲かつ高精度な新たな手法を開発している研究者がいるかもしれません。そういった情報を得たいです。
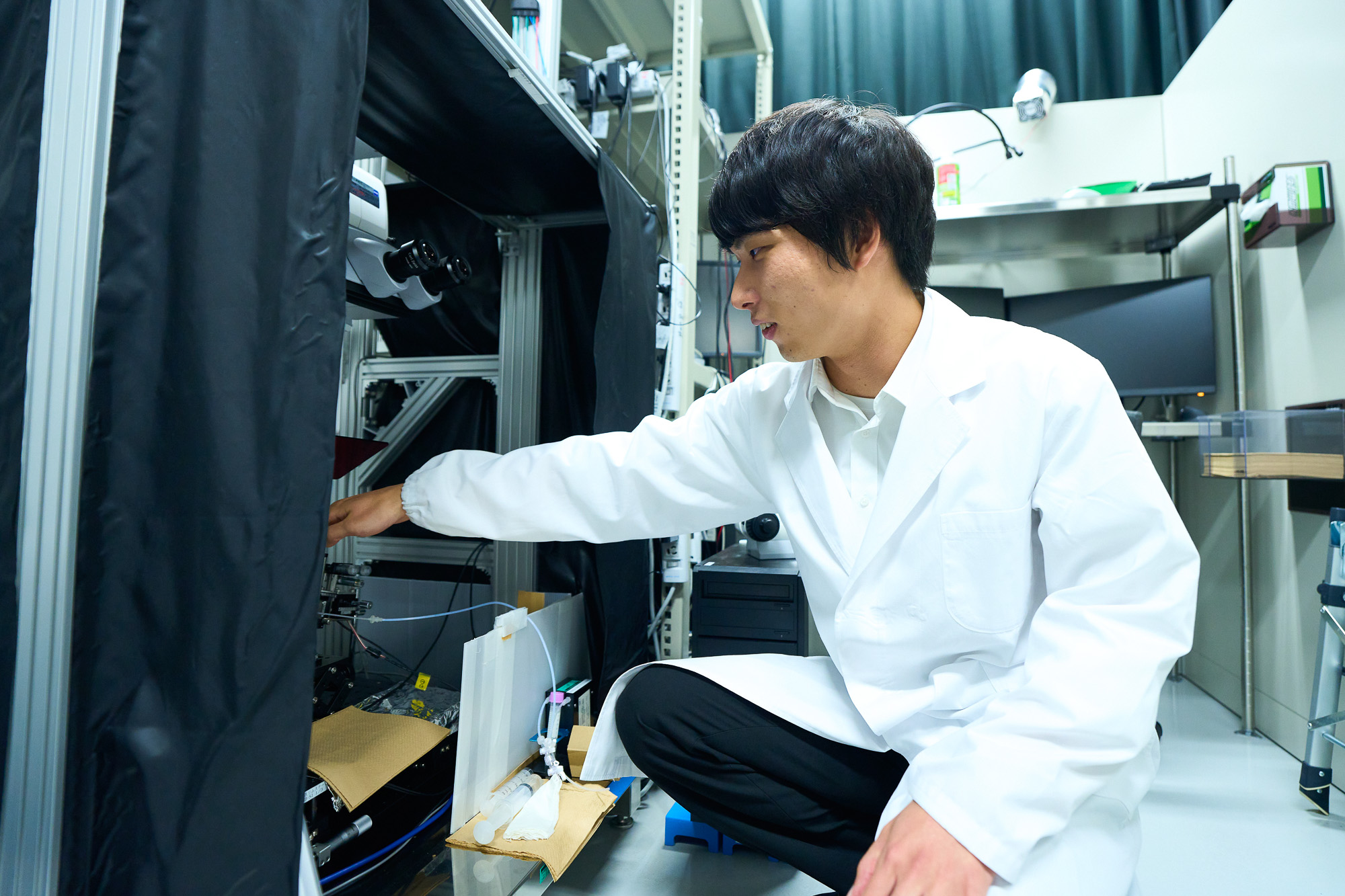
今回のシカゴ訪問にあたっては、英語プレゼンスキルを学ぶためのセミナーに参加しました。これもプロジェクトによる支援の一環です。今回、初めて1人で渡米するにあたり不安は多くありますが、セミナーで磨いた英語力が役立ってくれることと期待しています。
モノづくり業界は今、自動運転の自動車に代表される ように、自動化を進めています。これは、「ヒトの操作を支援する技術」だと言え、カメラや各種のセンサーが支えています。ではヒトの操作を支援する技術をさらに進化させるために何が必要かというと、ヒトの状態をより適切で精細に把握することです。脳波や筋電位、心電位、表情、姿勢などの 生体情報を得て運転者の心理状態や疲労度が把握できるようになれば、空調や照明、音楽などを調整して快適性を増すことができるでしょう。操作に介入して安全性を高めることもできるでしょう。
現時点では人間が自動車をはじめとした機械を操作するとき、人間の意図と実際の機械 の動きに差が生じてしまい、意図通りの操作ができないという状態が起こり得ます。これを解消するには、今のところは人間が操作技術を学んで向上させるしかありません。しかしより精細にヒトの状態をとらえられるようになると、例えば脳波や筋電位から「この人は今、こんな操作がしたいのだな」と読み取ることができるでしょう。そして、読み取った情報に合わせて機械が自分で動いてくれるようになるはずです。私はこれを、「ヒトに焦点が当たり、機械がヒトに歩み寄る技術」だと考えています。現在のように、ヒトが機械に合わせ、歩み寄ろうとする技術とは逆です。こういった技術の研究開発が今後加速し、人間と機械の距離が縮まっていくのではと期待しています。
「未来を見据えて挑戦する」創立者の姿勢が受け継がれている

同志社大学は私にとって、工学分野から脳科学分野へ移って両者の融合を目指すというチャレンジを受け入れてくれた大学です。このような環境が整った背景には、やはり創立者である新島襄の精神があると思います。新島襄は自由を求め、当時の国禁を破ってアメリカへ渡りました。帰国後は「良心」と「自由」に満たされた学園と社会を実現すべく同志社大学の前身となる同志社英学校を設立しました。そういった「未来を見据えて挑戦する」姿勢が現代に受け継がれた結果、誰もが挑戦できる環境ができあがったと思います。若手研究者の挑戦を後押しする今回のプロジェクトも、まさに新島襄の精神の表れだと感じています。
進学や就職、新しいコミュニティーへの参加など、何か新しいことをする際には不安がつきものです。研究も同じで、未知へのチャレンジは孤独であり不安がつきまといます。なぜなら、誰も見たことのない世界を見ようとしていて、誰も経験したことのない出来事を経験しようとしているからです。でもそこにはきっと、わくわくするような何かがあるはずです。研究でいえば、人間が活動できる知識領域の拡張という成果が待っているはずです。私は、このわくわく感をずっと忘れずにいたいです。