“D”iscover -History-


History of DOSHISHA #2 〜150年の歴史をたどる〜
「温故知新」。未来への挑戦の指針を学びとるべく、積み重ねてきた歴史をたどる。同志社は新島襄を中心に、幾多の困難を乗り越え、志を同じくする人々の祈りの中から誕生しました。「150年の歴史をたどる」第2回は、同志社創立にゆかりの深い人物を紹介します。
「一国の良心」となる人物の養成を目指して

日本の将来を憂え、国禁を犯してまでアメリカへと渡った若者がいました。彼の名は新島襄。同志社の創立者です。1864(元治元)年6月、新島は21歳の時に函館から密出国し、上海にてアメリカ船ワイルド・ローヴァー号に乗り換え、約1年後にボストンに到着しました。ワイルド・ローヴァー号の船主A.Hardy 氏は、新島が海員ホームで書き上げたという「脱国の理由書」を読み感銘を受け、自身の母校であるフィリップス・アカデミーや、理事を務めていたアーモスト大学に入学させるなど、物心両面で新島を支えました。
新島は、アンドーヴァー神学校で神学を学び宣教師の試験に合格後、日本でのキリスト教の学校の設立を訴え、5,000ドルの寄付の約束を得て帰国。その後、大阪で学校設立を目指しましたが、キリスト教教育を認められず、京都府顧問に相当する役割を果たしていた山本覚馬らの支援を得て、京都で学校設立を認めてもらいます。しかし、保守的な人々の反対を危惧した京都府からの要請を受け、新島は学校で聖書を教えない条件を飲む形で、同志社英学校を開校しました。当初の教員は校長の新島とアメリカ人宣教師J .D .Davisの2人、生徒は8人でのスタートでした。新島はその後、私立大学の設立を目指して邁進し、英学校中退後、ジャーナリストであった徳富蘇峰の協力を得て「同志社大学設立の旨意」をまとめ、全国の新聞に公表します。そして新島の死後、彼の宿志を受け継いだ教え子たちが、ついに同志社大学設立に至りました。
同志社は、現在、幼稚園から大学まで約4万1,500人の学生、生徒、児童、園児の学ぶ一大総合学園となっています。卒業生はおよそ36万人を数えます。この国の未来を創るために。新島をはじめとする先人たちの思いを受け継いで、これからも同志社の歴史は続いていくことでしょう。

新島が渡米する時に乗船したワイルド・ローヴァー号の船主。新島の「脱国の理由書」を読み、感銘を受け、物心両面にわたって惜しみない支援を与えました。新島がアメリカの父として慕った人物です。

京都府議会議員(初代議長)として初期の京都府政に貢献。新島の同志社英学校設立計画を知り、旧薩摩藩邸の敷地を学校用地として新島に譲りました。「志を同じくする者が集まって創る結社」から「同志社」と命名した人物です。
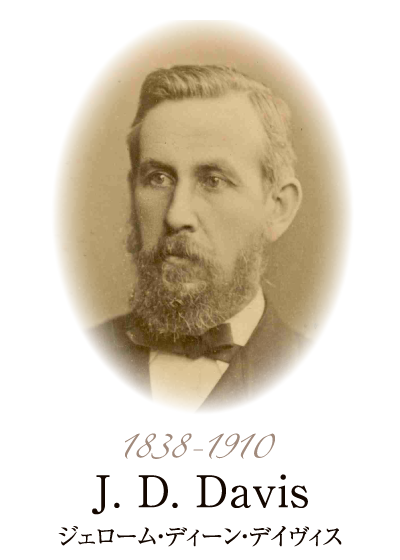
アメリカ人宣教師で、同志社英学校創立時の教員の1人。神戸で宣教師として活動していましたが、1875(明治8)年、同志社英学校を開校する新島を手伝うため、京都に移り住みました。
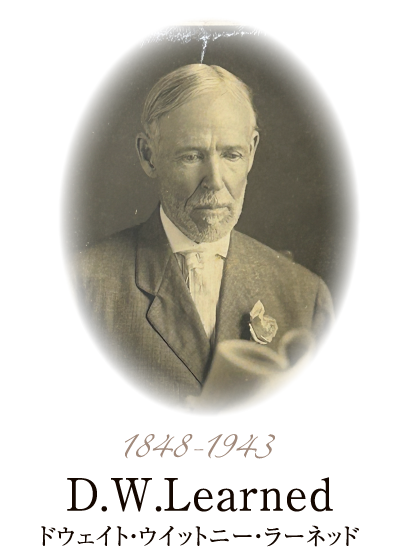
同志社発展に貢献した一人。新島襄の志を支え、半世紀にわたって同志社で教壇に立ちました。京田辺校地の「ラーネッド記念図書館」に名前が残され、彼が愛した言葉〝Learn to Live and Live to Learn〟が建物に刻まれています。
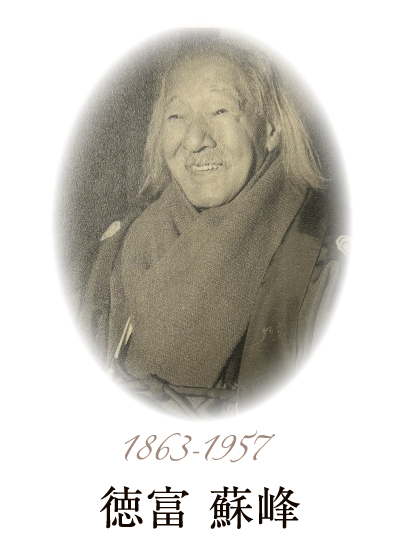
「同志社大学設立の旨意」は1888(明治21)年、同志社英学校の創設者である新島から材料の提供を受けて、徳富蘇峰が内容を考えたといわれている。新島が永眠する際には、一切の遺言を蘇峰が筆記したといわれています。

創立からの歴史を振り返る変化し続けるキャンパス|同志社大学VISION2025特設サイト