“D”iscover -Opinion-


発想の転換がもたらした待望の解毒剤 ~火災ガス中毒から命を守る救急救命用治療薬の開発~(後編)
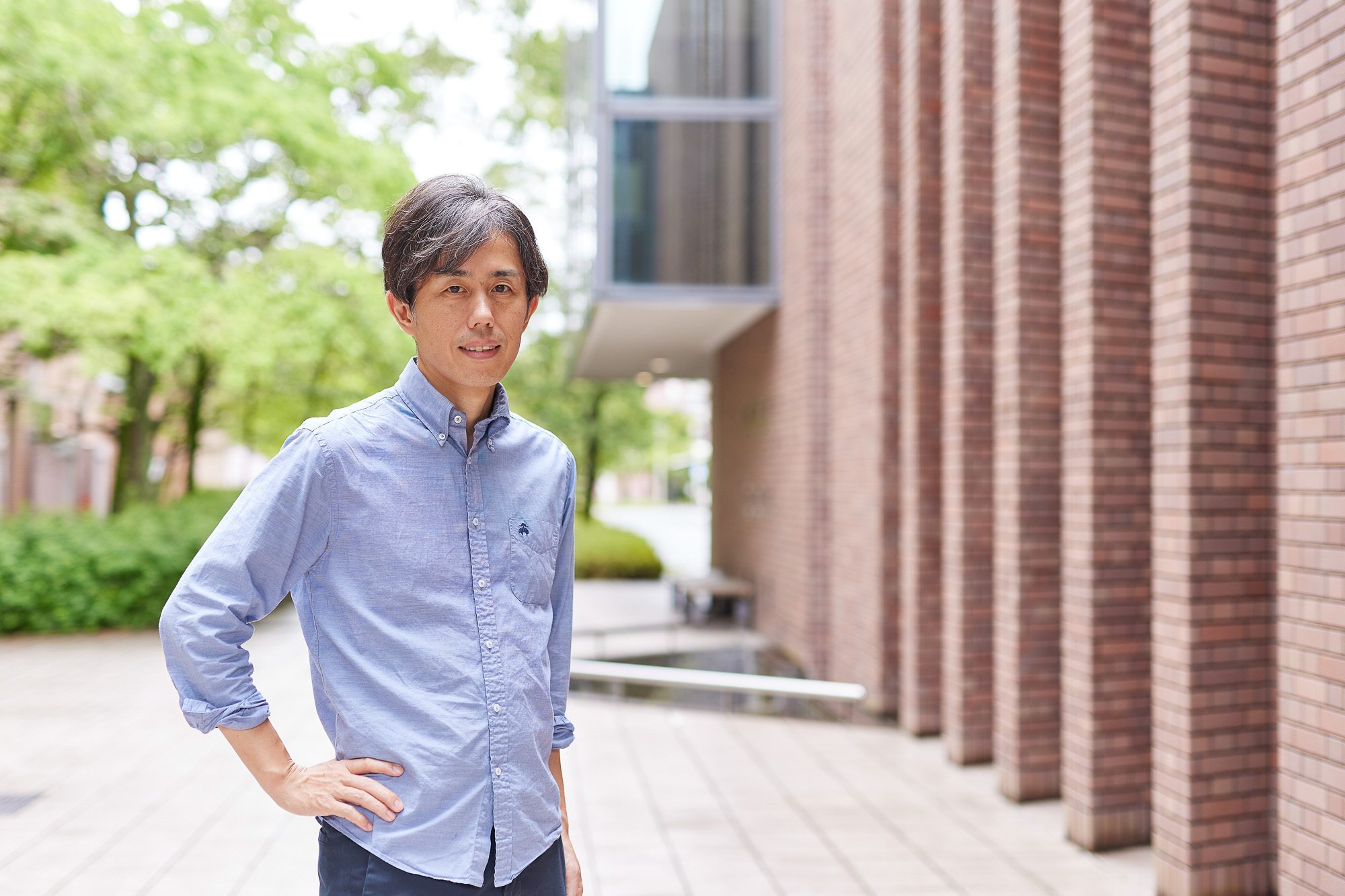
スタートアップを設立し、医療実装を目指す

今後の目標は、hemoCD-Twinsを医薬品として実用化することです。そのためには私自身がスタートアップを発足させることを計画しています。2025年くらいには会社を設立し、そこから2年をめどで非臨床試験、さらにその後の4~5年で臨床試験を行いたいと考えています。合計で言えば、今から8年後が医療実装の目標時期です。
以前は、私たち大学の研究者が医薬品の元となる化合物を開発すれば、あとは医薬品メーカーが引き取って臨床試験などを行い、実用化してくれると考えていました。しかしそのような例はごく限られます。医薬品メーカーがターゲットにするのは、高血圧や糖尿病などのように、患者数が多く市場性を見込むことができる薬です。対する火災ガス中毒は、年間の死亡者数が500人ほど。莫大なコストを投じて薬の開発を行うには市場が小さすぎます。かといって、その500人の救いとなり得る研究を、市場性という理由であきらめたくはない。だから自らの力で医療実装を目指します。
もちろん、大学発の医薬品開発である「アカデミア創薬」には数多くのハードルがあり、うまくいかなかった例も少なくないことは認識しています。最近では、やけど治療の専門医が参加する「日本熱傷学会」で講演を行い、意見交換を行いました。そういった現場の方々と連携することでしっかりとニーズをつかみ、市場に受け入れられる薬を生み出したいです。2024年3月からは公的資金を受けることもでき、hemoCDの大量合成や救急救命の専門医の方との共同研究もスタートしました。
現在、世界中で人工血液の研究が進められています。hemoCDは「酸素運搬機能を復活させる」という働きを持つ人工血液だと言うことができます。hemoCDを実用化することは、人工血液の実用化なのです。今のところ、医療実装された人工血液はありません。せっかくなら一番乗りをしたいです。そのチャンスがhemoCDにはあると考えています。
マイノリティになることを恐れず、興味の探究を

スタートアップを設立して医療実装を目指すという点において、同志社大学は非常に恵まれた環境です。偶然ですが、スタートアップの勉強をしようと思って検索し、購入した本の著者が、本学商学部の先生(冨田健司教授)でした。さっそく先生にメールを送ったところ、すぐに直接お話する機会をいただいて、いろいろと教えていただきました。また研究支援課には、スタートアップ支援を職務とする職員が赴任されて、さっそく相談に乗ってくれています。学内という身近な場所に様々な専門家がいることは、とても心強いです。
これは同志社大学に限った話ではありませんが、研究者を目指す若者が減っていることに私は不安を感じています。近年では学部を卒業後、大学院の修士課程へ進む理系学生は確かに増えました。しかしその先の博士課程まで進む人となると、ほとんどいません。その理由はというと、「修士で修了して企業に就職する人が多くて普通だから」です。つまり、マイノリティになることを恐れているのです。
人とは違うことをしてこそ価値があるのが研究です。企業での研究では、上から明確にゴールが定められ、その成果が問われます。一方、大学の研究は違います。興味があることを自由に探究できて、当然ながら失敗も許されます。人工血液の実験に“失敗”したことが、火災ガスの解毒剤につながったというhemoCDの開発は、その格好の例です。どうか、人と違ったことをしてください。喜んでマイノリティになってください。最終的に社会から求められ、輝きを発揮するのはいつの時代もマイノリティです。
同志社大学は、博士課程の学生を支援する様々な仕組みが整っています。学費が免除され、研究費や生活費を支給する制度もあります。小学生や中学生のときに「研究をしたい」と目を輝かせていた気持ちをそのままに、博士課程まで進んでこられることを期待しています。そしていつか、同志社大学の教員として、次の世代の研究者を育てていきましょう。
北岸 宏亮
同志社大学理工学部機能分子・生命化学科教授。博士(工学)。主な研究分野は有機化学、生体関連化学など。同志社大学工学研究科工業化学専攻修了。大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻博士研究員を経て2008年より同志社大学で教育・研究に従事。2020年より現職。