以下、本文になります
地球と宇宙を展望する~宇宙時代における大学の使命~
同志社創立150周年記念(大学事業)公開シンポジウム
毛利氏と小原学長の対話の様子はこちらからご覧ください

パネルディスカッション テーマ
宇宙と私たちのこれから
登壇者
- 毛利 衛 氏 宇宙飛行士・日本科学未来館名誉館長
- 小原 克博 同志社大学長
- 上野 宗孝 氏 JAXA宇宙探査イノベーションハブ 技術主幹
- 金津 和美 同志社大学 文学部教授
- 渡辺 公貴 同志社大学 生命医科学部教授
- 桝 太一 同志社大学 ハリス理化学研究所助教
モデレーター
後藤 琢也 同志社大学副学長
多様な視点から見る「宇宙と私たち」
- 後藤
- パネルディスカッションでは「宇宙と私たちのこれから」をテーマに議論いただきます。まず自己紹介と、宇宙とのつながりをお聞かせください。
- 上野
- 私はもともと宇宙物理学の研究者で、宇宙自身を研究していました。JAXAでは多くのミッションに携わり、最近は「宇宙探査イノベーションハブ」で、月や火星への人類進出の実現を考えています。我々は地球を離れた環境で生きていけるのかという挑戦のステップに入っています。また、宇宙ビジネスにも広く関わっています。先ほどの対談では国益の戦いというお話も出ましたが、今や私企業間の戦いも始まっています。完全に資本主義社会に入っていく。より危険な状況が訪れる可能性もあるため、さまざまな立場で話をさせていただきたいと考えています。
- 毛利
- 今のお話をわくわくしながら聞きました。先生方には、その研究が人類的な喜びにどう関係するのかも伺いたいです。
- 渡辺
- 同志社大学生命医科学部医工学科の渡辺です。私が開発に参加した超小型の変形型月面ロボット「SORA-Q」は、昨年1月20日に月面に到達し、写真を撮影して地球に送ってくれました。こんな小さなロボットが月面で動くのは奇跡的ですが、地球での十分な実験によって絶対に撮れるという自信のもとに、JAXA、タカラトミー、ソニー、同志社大学が協力して月面に送り込んだものです。今まで同志社大学では宇宙教育のようなことがあまり行われていなかったのですが、私の研究室の学生には、宇宙開発、人類の探究を続けてほしいと願っています。
- 桝
- 同志社大学ハリス理化学研究所の桝太一と申します。スペースシャトル・コロンビアが初飛行した1981年生まれで、毛利さんのエンデバーに影響を受けました。日本テレビでアナウンサーをした後、現在は同志社大学で、特に地上波テレビを通した科学コミュニケーションの研究をしています。これは「科学はみんなのものであるべきだ」という思想に基づいています。そのために、衛星地球観測コンソーシアム(CONSEO)の広報アンバサダーとして、市民向けの解説動画のMCも務めています。テレビ番組「真相報道バンキシャ!」でも宇宙を扱っています。したがって今日は、市民の皆さんと宇宙とのつながりという文脈でディスカッションできればと思います。宇宙は身近だと言われますが、果たして私たちの気持ちの距離は本当に身近でしょうか。今後、大学教育も含めて、私たちは宇宙をどう伝え、どう受け止めればいいのか。宇宙は科学に紐づけっぱなしでいいのかという点も含めて、議論できればと思います。
- 金津
- 本日は、科学から最も遠い文学部にいる私に声をかけてくださったことに感謝します。私は文学部英文学科でイギリスの詩作品を研究しており、特に環境批評または環境文学の分野で、文学作品が自然や環境をどう語るのか、文学を通して環境問題をどう考えるかという研究に取り組んでいます。私の研究分野については、毛利先生の『わたしの宮沢賢治 地球生命の未来圏』を参考に紹介させていただきます。私は環境文学の視点から研究を進めるうち、宮沢賢治の世界観の奥深さに魅了されました。賢治の作品や論評も読みましたが、毛利先生のご論考には心を動かされました。本書には「詩人の感性」と「生き延びる」という言葉がありました。毛利先生が宇宙授業で賢治を紹介するとともに、詩人の感性が必要だというメッセージを届けようとしてくださったことは、文学研究者として嬉しかったです。最近の環境文学では、持続可能性よりも「いかに生き延びるのか」という「レジリエンス」に強い関心が寄せられています。毛利先生の宮沢賢治論は、現代の環境文学研究においても非常に先進的な問いに答える優れた研究です。私自身は文学を通じて「生きる喜びとは何か」「生きるとは何か」を考え、それを自分自身の問題、地球環境の問題、他の生物とのつながりとして共有する場を提供していきたいと考えています。
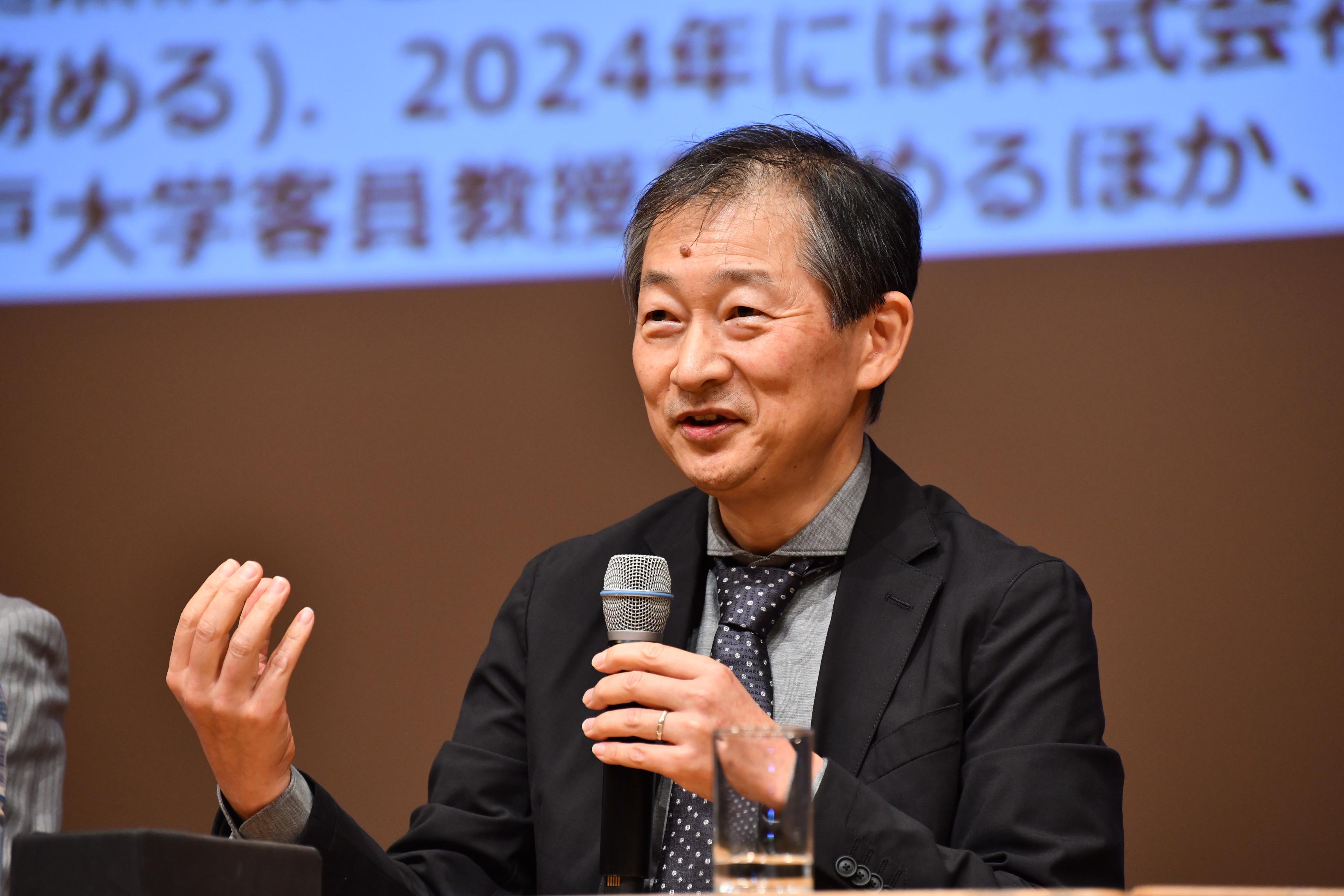
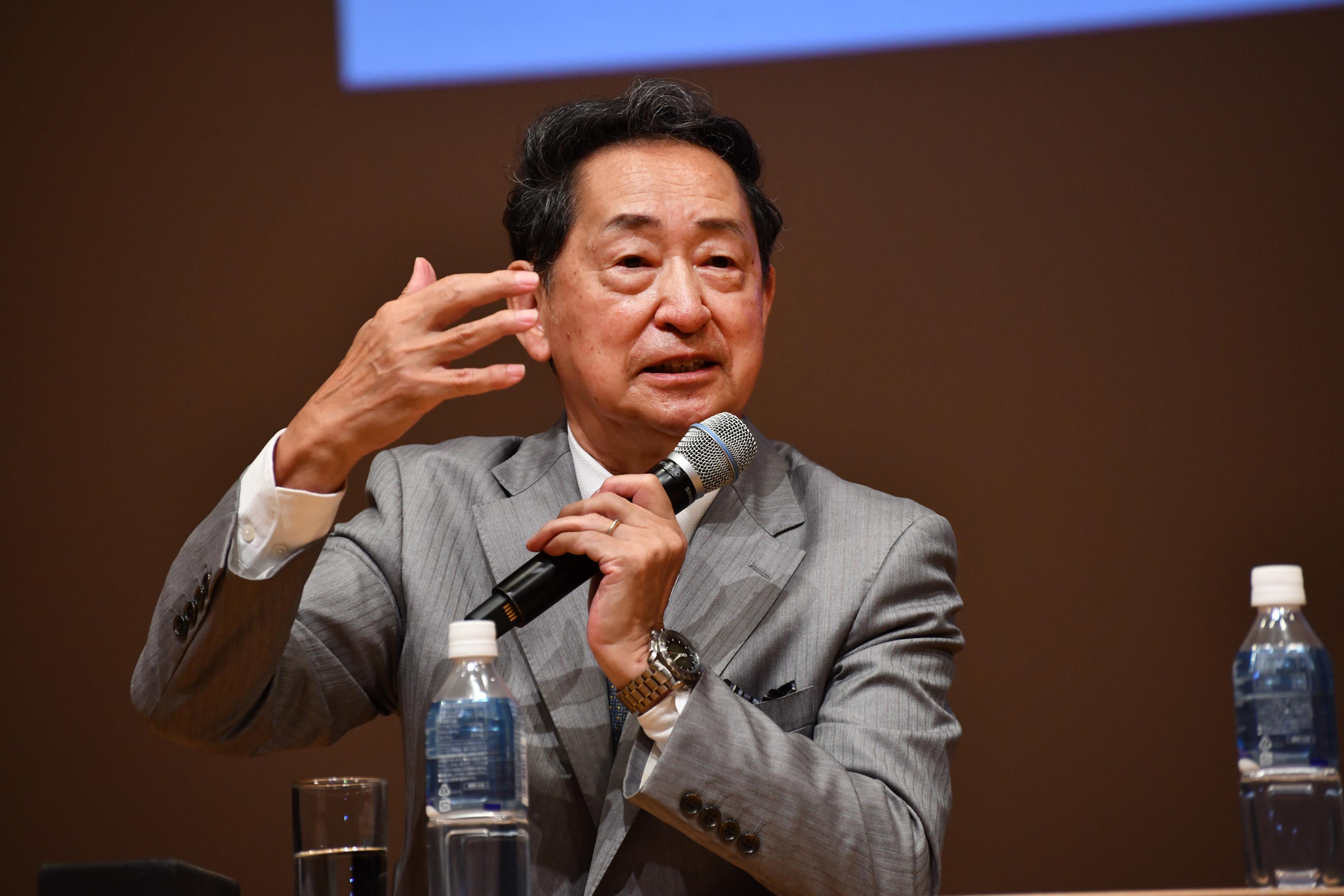

変化する「宇宙」の認識 〜意識と現実とのギャップを考える~
- 後藤
- ありがとうございました。「つながり」がキーワードとして浮かび上がりました。次に、我々一般人が宇宙を身近に感じ、かつ生きがいを感じて生きるにはどうすればいいか、同志社大学はどう応えるべきでしょうか。学長からお願いします。
- 小原
- 桝先生の問いにもあった「宇宙との気持ちの距離」みたいなものは、私もずっと考えてきました。昔の人々は夜空を見上げ、きらきら輝くあの世界と自分はどう関係しているのかを考え、神話などに記しました。昔の人は宇宙との距離が本当に近かったと思います。しかし今、私たちは空を見上げるより、手元のスマホを見ています。スマホは便利ですが、夜空を見上げて宇宙との関係を考えるような時間は取り戻すべきではないか。私の幼少期はスペースシャトルの時代で、私はガンダム世代でもありました。宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』を読み、アニメの「銀河鉄道999」も流行り、宇宙は本当に身近でした。宇宙開発には低迷期もありましたが、私にとって宇宙は今も近い存在であり、人生観、世界観の源泉です。
- 桝
- スマホはGPS衛星を使っていますから、昔より技術的には宇宙が近いわけです。毛利さんはかえって今の方が、宇宙への憧れや気持ちが遠くなっていると感じますか。
- 毛利
- それが、宇宙が近づいたという証明かもしれません。逆説を言うと、遠いから宇宙なんですね。「宇宙」という言葉は、人間にとっていつも手が届かない部分を表現している「夢」もあるのではないでしょうか。近づいてビジネスになると、もう憧れの宇宙じゃないんですよ。私も宇宙飛行士に選ばれた途端、宇宙は夢ではなく現実になり、失敗できない「挑戦」と同時に「こなすべきもの」になりました。
- 渡辺
- 幼少期は宇宙に興味を持つ子が非常に多いですが、その後急速に興味を失います。情報があふれすぎて、逆に宇宙が近くなりすぎているのかもしれません。YouTubeにはNASAが飛ばした衛星の素晴らしい画像があふれている。だからすごく身近で、その先へ進むのは少数だと思います。
- 上野
- 私はもともと宇宙が研究テーマだったので、根源的な憧れはずっと持っています。一方で、携帯やネットワーク、気象データなど、衛星から送られるものを我々は何気なく使っています。そういう意味では、思っている以上に身近な部分は多いでしょう。一方、宇宙開発は国がやるものだと思われがちですが、世界の宇宙活動の規模を金額ベースで言うと、企業レベルの活動が全世界の宇宙機関の予算を完全に上回っています。日本ではまだですが、世界では完全に逆転しています。宇宙は利用する場所としての位置づけが強まっているのです。2040年には、自動車マーケットと逆転する経済規模になる可能性もあると言われています。そうなるとさらに競争は激しくなり、宇宙はさらに開拓されるでしょう。それは人間の欲望を駆り立て、前に進む部分もあれば、逆に困ったことになる両方がある。いずれにしても、もう普通のインフラの場になりつつあるのが最近の状況です。



宇宙の活かし方と「文理融合」の視点
- 後藤
- では、この宇宙をどう活かしていけばいいでしょうか。
- 桝
- 金津さんにお聞きしたいのですが、文学が人の心の象徴だとすれば、宇宙を扱った文学も時代とともに変わってきているのでしょうか。
- 金津
- 文学者としての宇宙体験について考えたとき、私のイメージする宇宙として、谷川俊太郎の「二十億光年の孤独」という詩が思い浮かびました。「億光年」という言葉の力に惹かれます。時間と空間をまったく超えたような言葉の力、これが宇宙の絶対的な大きさなんだなと感じました。それが私にとって初めての宇宙体験だったかもしれません。この詩が非常にいいなと思うのは、戦後間もない1950年に19歳の谷川が、現代の学生が持つのと同じようなリアルな不安を描いていることです。また、宇宙は決して遠いところにあるのではなく、今ここ、私たちの足元にあるという感覚が生まれてくるところもすごく素敵です。不安や孤独と向き合うことで、自分の宇宙が広がっていく。このように文学を活かすことができればと思います。
- 後藤
- 宇宙は足元に広がり、すべてつながっているのですね。
- 毛利
- 会場にいる理系の学生さんは、金津先生のお話をどう聞きましたか。
- 学生
- 私は理系で修士の2年です。学部生の頃、小原先生の良心学の授業を履修しました。文理融合の授業でしたが、理系だから理解できないことはなく、むしろ理系だからこそ見える側面のあるレポート課題もありました。文系理系という区別をすることなく講義が進んでいたのは非常に印象的でした。
- 小原
- conscience(良心)と言う英語には「共に知る」という原義があり、さらに遡ってラテン語でもギリシャ語でも同様で、科学と非常に関係していることを、良心学の授業の中で話しました。科学的思考と人文社会系の思考は別々ではなく、むしろ一緒に見ることで、単独では見えない世界が見えてくることを示すのが、良心学の狙いの一つです。
- 桝
- 毛利さんに伺いたいのですが、最近、宇宙飛行士の応募資格が理系限定ではなく、人文系も含めるようになったと思います。どう捉えていらっしゃいますか。
- 毛利
- NASAの宇宙飛行士はコンピュータを扱い、感覚的ではない論理的な思考が必要なため、危機管理の意味でも理系の人を選んできました。しかしJAXAではミッションのために仕事ができるのであれば、2021年度から理系文系を問わなくなりました。宇宙飛行士に応募する母集団を増やしたいという意図もあるでしょう。次の時代には、知識の偏差値に関わらず、人類が生き残るためにどういう能力を持つ人がいるのかが重要になります。大谷選手のように、ピッチャーとバッター両方ができるような人材を期待しているのです。
- 渡辺
- 同志社大学には、文系出身で情報系の会社に勤めた後、エンジニアになり、宇宙ベンチャーを作った素晴らしい先輩がいます。彼は現在、世界的に有名な月面ロボット会社のCEOです。文系の学生でも、本当に志と努力があれば理転は十分に可能です。理系の学生でも、文系の人が多く行く職種に就く人もいます。一番重要なのは、学生のときに多くを学び、目的を持って何かに挑戦していくことです。
- 毛利
- 「楽しいですか?」ということの方が大事になると思いますね。

宇宙との関わりを通じて人生を楽しく送る
- 後藤
- 最後に、宇宙というプラットフォームに我々が軸足を置いたとき、どう宇宙と関わりつつ、楽しく人生を送ればいいのか。そのためのメッセージを、特に学生諸君へひと言ずついただければと思います。
- 小原
- 毛利先生が基調講演の結論で語ってくださったように、能力を最大限発揮する中に、生きる喜びが生まれるのだと思います。教育とは、人の隠れた能力を開発することです。将来の安定だけでなく、人として生きる喜びを感じられる教育を施すべきです。ところが残念ながら、日本の高校までの教育では、学ぶことが負担になっています。学ぶこと自体が生きる喜びにつながっていない。むしろ生きる喜びを制限して勉強しないといけない。そのギャップを埋め、学問を通じた成長の中に大きな喜びを感じられるような道を増やしていきたい。新島襄自身も、自分の好きな事をとことん極めたいという、たぎるような好奇心を持っていました。私たちは若い頃も、この年代になっても、そういう好奇心を持つべきだと思います。
- 金津
- 谷川俊太郎の「二十億光年の孤独」に、「万有引力とは / ひき合う孤独の力である」という言葉があります。大学は、それぞれが持つ孤独をひき合う「万有引力」の場であってほしい。私も教育者として、そのような場としての大学を目指したいです。この詩には、宇宙という無の世界を人間的な言葉の世界に変えていくような力強いユーモアがあります。こういう力強いユーモアに満ちた詩人の感性といったものを育むような場が大学であってほしいですし、これからの世界にますます必要になってくるのではと思います。それによって、私たちは生きる喜びを見出していくのではないでしょうか。
- 桝
- これから宇宙に関わる方々は、人文系、理工系の両方の視点を兼ね備えてほしいと思います。科学は不可欠な要素ですが、それだけではおそらく宇宙との距離感はつかめないかと思います。逆に人文系の視点だけではもったいない。まさに両方の視点を持った形で宇宙に携わっていってほしいです。「文系だから」「理系だから」という時代ではなく、それは宇宙でも例外ではありません。受験ではまだ分離しているかもしれませんが、そういった壁は自分たちで越えてしまえば大丈夫です。ぜひこれからの宇宙を、人文理工の両方の視点を持って切り開き、新しい価値観、新しい時代を作っていってほしい。同志社大学がその後押しをできればと願っています。
- 渡辺
- 私は今、大変楽しんで学生と一緒に研究しています。SORA-Qが宇宙に行ったからだけでなく、研究が楽しいのです。宇宙にあまり関心がない学生も中にはいますが、自分の研究に楽しみを見つけるのが重要です。楽しまなければ損です。適当に論文を出して卒業しても、のちのち後悔します。私も学生と一緒に楽しめる研究をしていけたらと思います。
- 上野
- 成功した事業家の中には、お金儲けだけでなく、人々を便利にして幸せにしたいという思いで活動し、結果としてそれが大きなビジネスになるケースも多いと思います。これから宇宙も新しい場所となるので、そこを使ってどうすれば皆が幸せになれるかを一緒に考える必要があります。これは理工系だけの話ではなく、どう皆と宇宙をつなげていくかを考えるのですから、やはり総合的な見方が必要になるでしょう。これがビジネス的展開です。もう一つ言いたいのは、月や火星を目指すことで、人間が地球から独立して生きていけるかどうかという段階に、我々が踏み込もうとしていることです。もしかしたら我々の一部が、将来本当に宇宙人になっているかもしれない。そのステップに我々が踏み出せるかどうかの瀬戸際かなと思います。そこを乗り切ることができれば、地球以外の場所にも人間がそのうち住んでいるかもしれないという、いよいよSFではないところに来るのだろうと思います。
- 毛利
- 私が実際に宇宙に行き、一番認識したのは「地球ってありがたいな」ということでした。宇宙では、私たちは地球環境を模擬した生命維持装置の人工空間の中だけで生きられます。私たちは宇宙船や宇宙服の中では地球から運んだ人工の空気を吸い、水素と酸素から合成された水を飲んで生活し、宇宙から帰ってきました。地上に帰還し宇宙船のハッチが開いて外の空気が入ってきたとき、ケネディ宇宙センターの沼地の匂いや湿度が皮膚を覆い、言われもない安心感を覚えました。地上待機の宇宙飛行士が差し出してくれたコップ一杯の冷たい水を飲んで「うわぁ、美味しいな」と思いました。地球の水は自然のミネラルを含み、本当に美味しい。人間は他の生命と一緒でないと持続的に生きていけないと実感しました。私たちは人間の形のまま人工空間だけでは、世代を超えて宇宙に住む生物にはならないでしょう。私たちが、地球に生を受けて多様化した生命の一つとして宇宙に興味を持ち、宇宙に行くというのは、結局は地球生命として40億年生き延びてきた知恵を学び未来へつなげることだと、はっきりわかりました。人間だけで地球を捨てて月や火星に移住することは不可能です。多様な地球生命と一緒でなければ人間は世代を超えて持続的に生きられないと思います。今、他の生物も一緒に連れていく宇宙研究をしていますが、最終目標は、80億人になった人間だけでなく、次の世代に向けて、地球生命が地球環境で生き延びていけるかどうかに貢献することです。それが一番の喜びではないかと思います。そういう意味で皆さんの研究や勉強は、将来へ向けて人類、そして地球生命を未来へつなげるという、非常に価値の高い人間にしかできないことなんですね。今日は学生さんからの質問を聞き、同志社はすごいと思いました。素晴らしい先生方と学んで、同志社はこれから200周年に向けて発展していくだろうと期待しています。
| 関連情報 | 同志社大学公式YouTubeチャンネル 当日の様子(動画)は上記リンクよりご覧ください。 |
|---|