“D”iscover -Campus-


多様な文化で彩られた豊かな社会を目指して ~京都の伝統産業×学生によるソーシャルビジネス~(中)

ソーシャルビジネスへの興味と京都へのあこがれが出発点
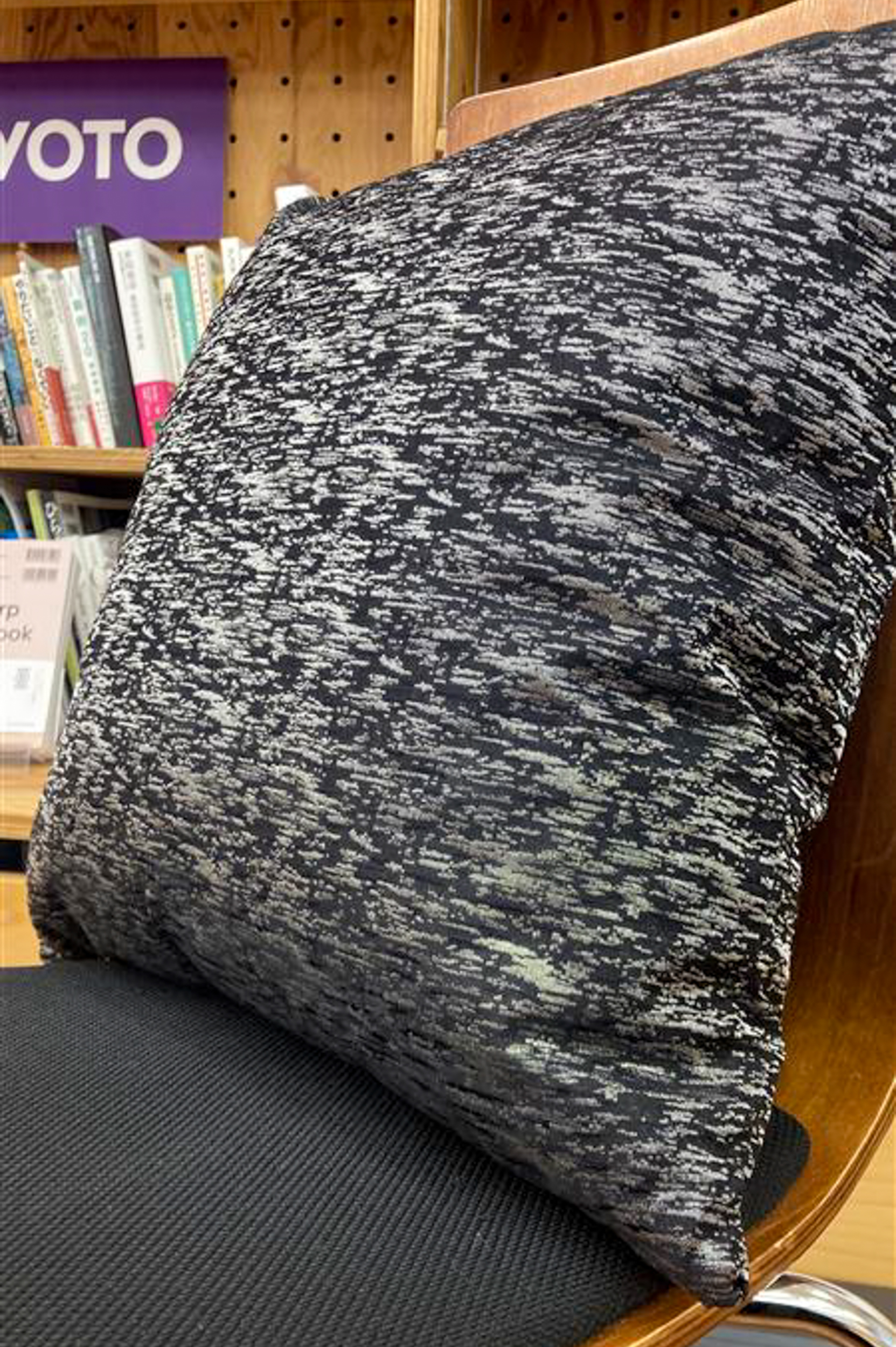 クッションカバー
クッションカバー
伝統産業が活気を失った大きな要因は、戦後以降の急速な暮らしの欧米化です。衣類は和服ではなく洋服が一般化しました。すると着物や帯、履物、小物など、和服に関連する様々な品の需要が減少し、産業が縮小しました。食事も欧米化すると、和食で主に用いられていた漆器の出番が減りました。化学繊維やプラスチックなど、工業技術の発達も伝統的なものづくりを追いやっていきました。
需要が減ると職人さんの所得が減ります。すると後継者を育成する余力がなくなったり、設備投資などができなくなったります。結果、新しいことができずに時代のニーズから取り残されていき、さらに需要が減ります。このような負のサイクルが生まれているのです。京都に来て職人さんが講師を務めるイベントなどに参加するなかで、こういった課題を知りました。一方で、工芸品としての美しさや機能性はもちろんのこと、日本人が伝統的に受け継いできたものづくりや暮らしへの思いも知りました。それらを知ってもらうことが伝統産業の活性化につながると考え、活動を始めました。伝統工芸が持つ魅力や秘められた思いを理解し、暮らしに取り入れることは心が豊かになることにもつながります。社会を豊かにする可能性も秘めています。これらもまた、活動の原動力になっています。
伝統産業は「豊かさ」のヒントにあふれている
 アイマスク
アイマスク
様々な魅力を備えた伝統的な工芸品ですが、何といっても最初に浮かぶのが美しさです。職人の丁寧な手仕事が形として表れている美しさは、決して工業製品では表現できないものです。特有の温かさといってもいいでしょう。
二つ目の魅力は、社会を豊かにする力を秘めていることです。効率を追求し、大量生産される工業製品は、いわば均一さが特長です。対する伝統工芸品は、手作業ですから決して均一ではありません。同じような工芸品であっても、地域によって材料が違ったり製法が違ったりして、多彩です。つまり工芸品とは、多様さを象徴するような存在と考えることもできるのです。私は、多様な美しさが共に存在している社会こそが美しく、魅力的だと考えています。均一な工業製品では実現できない美しさ、豊かさです。そういった可能性を、伝統産業は持っているのです。
三つ目の魅力は、自然との関わり方の素晴らしさです。伝統工芸品の材料は、自然からのいただきものばかりです。いただいたものですから、余すところなく大切に使い切ります。自分たちの生活に必要な量以上を自然から奪ってくることもありません。材料の特性を理解し、うまく活用する知恵もあふれています。さらに、世代を超えて使い続けることも珍しくありません。「サステナブル」なんて言葉がなかったずっと昔から、私たち日本人はサステナブルなものづくりや生活をしていたのです。それを工芸品は教えてくれます。
これらの魅力をより多くの人に伝えるためにも、ショッピングサイトとコミュニティーの運営をしっかりと継続していきたいです。これからは今まで以上に、物質ではなく精神の豊かさを多くの人が求める社会になっていくと私は考えています。地域に根ざした多様な文化と自然が受け継がれた社会は、間違いなく精神的な豊かさをもたらしてくれます。もちろん、安全で快適な生活を支えるテクノロジーを否定するつもりはありません。両者のバランスが取れた社会の実現を目指して、伝統産業の活性化という側面から貢献していきたいです。