“D”iscover -Campus-


職業訓練は異なる時代や社会を映し出す鏡。誰もが笑顔で働ける社会の実現を目指して
~同志社大学 若き研究者の挑戦~(前編)
同志社大学は、多様化・複雑化を増す社会課題に挑戦し、新たな領域の開拓やグローバルな活躍を目指す若手研究者を支援すべく、「次世代研究者挑戦的研究プロジェクト(Spring! Doshisha)※」を実施しています。支援の対象となるのは、自由で挑戦的・融合的な研究に意欲的に取り組む博士後期課程の学生。研究活動に専念して研究力の向上を図ることができる環境の整備やキャリアパスの確保に向け、多彩な支援を一体的に受けることができます。プロジェクトの支援を受けながら職業訓練をテーマとした研究に取り組む、社会学研究科産業関係学専攻博士後期課程3年次生の霜永智弘さんに話を伺いました。
※本プロジェクトは国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の次世代研究者挑戦的研究プログラムの採択を受けて実施しています。
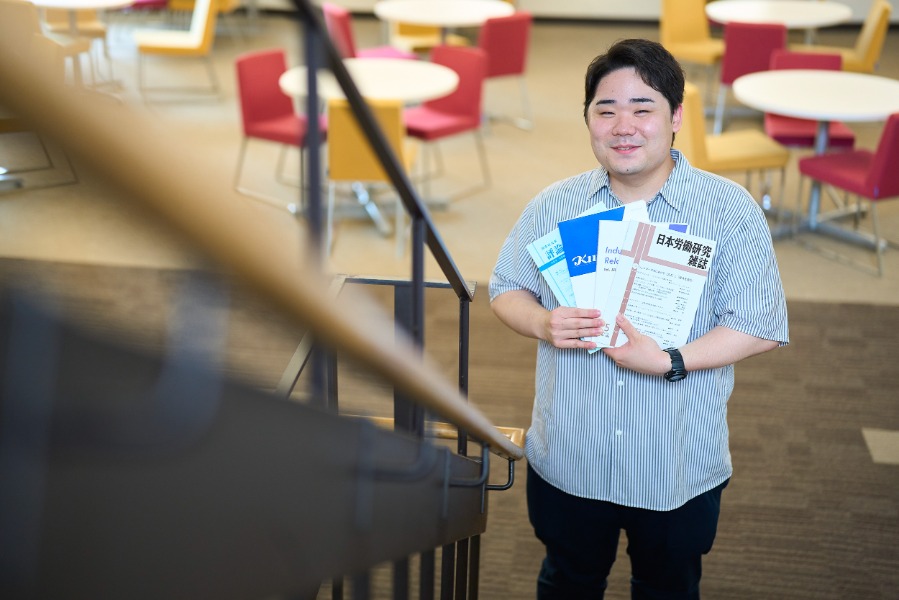
職業訓練のカリキュラムはどうやってできている? 成り立ちを知れば社会が見えてくる
「『職業訓練がキー概念!?』誰もが笑顔で働ける社会の実現を目指して」というテーマのもと、日々の研究活動に取り組んでいます。私は2016年に社会学部産業関係学科に入学しました。雇用や労働について学ぶユニークな学科で、そこで出会った興味が現在の研究に繋がっています。私が取り組んでいる研究活動のキーワードは「職業訓練」です。職業訓練とは「希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識などを習得することができる公的制度」のことです*¹。具体的に、日本における職業訓練は、主に求職者を対象とした新たな仕事に就くためのコース(離職者訓練)、中小企業などで在職中の労働者を対象としたスキルアップのためのコース(在職者訓練)、学卒者を対象とした専門技術を学び就職を目指すためのコース(学卒者訓練)という、計3種類があります*²。それぞれのコースにおいて「どのようなカリキュラムがあるのか」「そのカリキュラムはなぜ誕生したのか」「誰がどのようにそのカリキュラムを開発したのか」という職業訓練の成り立ちや運用の実態を明らかにすることが、私の主な研究関心の対象です。

現代の日本社会ではDX(デジタルトランスフォーメーション)が大きなテーマになっています。長期にわたる安定的な雇用は望みにくくなり、雇用の流動化・不安定化が今一度大きな課題になりつつあります。また「リスキリング」という言葉に象徴されるように、労働者が学び続ける姿勢やスキルアップへの取り組みがより一層求められるようになっています。それらを受けて職業訓練の現場では、デジタルスキルを学ぶための新たなコースやカリキュラムが編成されるようになりました*⁴。このように、職業訓練の変化の背後には、常に時代や社会の移り変わりが存在しているのです。
現場へのインタビューを通じて、日本における職業訓練の実態を正確に把握する
日本における職業訓練の仕組みを正しく知るためには、誰が、いつ、どこで、何を、どのように議論してきたのかを過去に遡って理解することが必要不可欠です。そこで、私は日本の職業訓練に関する研究レビューを行い、これまでの概念的展開を整理することから研究を始めました*⁵。その結果、「企業外での職業訓練と企業内での人材育成の関係性を明らかにすること」が、日本の職業訓練に関する議論を整理するための重要な手がかりになることが分かりました。
従来の先行研究では、しばしば「企業外での職業訓練と企業内での人材育成は、それぞれが切り離されたもの」として理解されてきました。身近な事例を取りあげるとすれば、「労働者の学び直し」を想像してもらうと良いかもしれません。これまでの日本では、先に述べた「リスキリング」をはじめ、「自己啓発」や「リカレント教育」への関心が高まっていました。社会を取り巻く環境が急速かつ広範に変化する中で、労働者が主体的に仕事で求められる能力を磨き続けることで、持続的な成長を遂げることができると考えられてきたからです。しかし、実際には「リスキリングを行っても自らのキャリアアップにはつながらない」、「自己啓発のみでは労働条件の維持向上を図ることが難しい」と感じる労働者が少なくないように思われます。それは、なぜでしょうか。具体的な原因についてはさまざまな視点から議論されていますが、結局のところ、これまでは企業の中で労働者に求められる仕事やそれに必要なスキルが十分に認識されずに、職業訓練の仕組みが構築されてきたことに問題があるのではないかと考えられています。このままでは働く人たちが十分に力を発揮できず、労働者が真に求める働き方を実現することができません。
こうした課題背景を踏まえて、近年は「企業外での職業訓練と企業内での人材育成は積極的に接続されるもの」として捉え直されつつあります。もし仮に、企業現場で求められる仕事とそれに必要なスキルを正しく理解し、それらに基づいて職業訓練のカリキュラムが設計された上で利用されれば、企業と職業訓練を受けた労働者の間に生じるスキルミスマッチが解消され、労働者は企業に就職した後も円滑にキャリアアップを実現できると考えられるからです。ただし、こうした検討が行われる中で、しばしば理論だけに偏った形で議論が進められ、社会の実態とかけ離れた机上の空論に陥ることがあります。このような問題を避けるためにも、まずは調査対象にできるだけ接近し、つぶさに観察しながら、既に存在する職業訓練の仕組み(ルール)について正確な実態把握を行うことが必要不可欠です。

そこで私は「教育訓練プロバイダー」、すなわち企業現場で労働者に求められるスキルや知識を提供する職業訓練の実施機関に着目し、そこで行われる「職業訓練のカリキュラム設計及びその管理運営の仕組み」を分析しています。より具体的には「RQ1:誰がどのようにしてカリキュラムを設計しているのか」、「RQ2:カリキュラムの設計において、何が情報源として活用されているのか」、「RQ3:誰がどのようにしてカリキュラムを実施しているのか」などを問いとして、日本国内における公的な職業訓練の実施機関を対象にインタビュー調査を行っています*⁶。
日本の職業訓練に関する研究成果は、これまで主に制度史として記述されてきたものが多く、現行の仕組みに関するデータは限られています。そのため、今後も継続的に現場を訪れ、そこで得られた事実や当事者の声を資料として蓄積していくことが極めて重要です。他方で、既存の先行研究を見渡すと、職業訓練を理解するための理論的枠組みが十分に設定されないまま議論が進められているものが少なくありません。今後の課題は、既存の諸理論との関わりを踏まえつつ、これまでの実態把握で得られたデータを活用して論文を執筆し、研究成果を広く世に問うことだと考えています。
*¹ 厚生労働省「ハロートレーニング(雇用・労働)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/hellotraining_top.html、2024年11月19日(火)最終閲覧
*² 霜永智弘(2024a)「わが国における公的職業訓練の制度概要とその歴史的変遷」『評論・社会科学』No.149、pp.57-71.
*³ 霜永智弘(2024b)「ポリテクセンターによる離職者訓練の運営と課題:ICTエンジニア科が生む包摂と排除の間隙」『評論・社会科学』No.148、pp.17-38.
*⁴ 霜永智弘(2023)「ポリテクセンターはスキルセンターの役割を担うのか:システム・ユニット訓練の運営と5つのキー概念に注目して」『第53回日本労務学会全国大会報告論集』pp.1-8.
*⁵ 霜永智弘(2024c)「わが国の職業訓練はどこに立ち、何がどう論じられてきたのか?」 『日本労務学会誌』第25巻、第2号、pp.20-40.
*⁶ 霜永智弘(2024d)「在職者訓練が持つ企業が求めるスキルニーズの分析機能:基盤整備センターでのカリキュラム・モデル設計を事例として」『2024年労働政策研究会議(日本労使関係研究協会)報告論集』pp.1-15.