以下、本文になります
第148号
第148号
ピックアップ記事
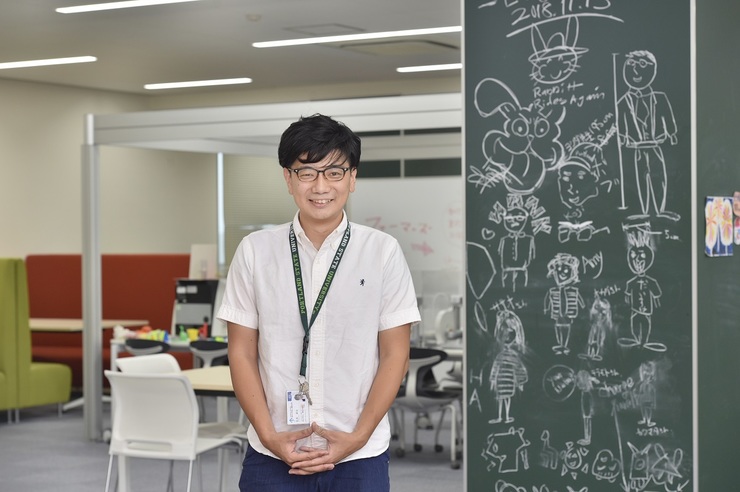
地域共創コーディネーター
松本 卓也(まつもと たくや)さん
| 1985年生まれ。大阪府出身。大学卒業後、電機メーカーでの社会人経験を経て、2011年より徳島県上勝町に移り住む。「百年続く町づくり」を合い言葉に、「上勝町を五感で感じられる」をコンセプトにしたカフェ「ポールスター」の経営を中心に、地域活性化に取り組む。2019年春からは、徳島大学人と地域共創センター、地域共創コーディネーターとして就任。活動領域を広げ、大学と地域との連携型学習、コミュニティベースドラーニングの構築に取り組む。大学時代はAIESECに所属し、国際的な政治・経済問題についての興味関心が強かった。それが今は人口1,500人、高齢化率50%の小さな町を拠点としている。人生は何が起こるかわからないが、だからこそ面白い。 |
地域の力をつないで生かす 自分の暮らしを自分で創る。上勝町から世界への挑戦。
妻のふるさと徳島県上勝町に二人で移住、そこで結婚。「ゼロ・ウェイスト(ゴミゼロ)政策」を推進する町に共鳴しながら、地産地消型のカフェ経営や産官学コーディネートなどを通して地域共創に取り組む卒業生です。

都会暮らしに疑問を感じ妻の故郷へ二人で移住
- ──
- 移住の決め手をお聞かせください。
- 松本
- 卒業後東京でメーカーに勤務していましたが、自分の生活をどこか宙ぶらりんに感じていました。東京では誰かのコントロール下でしか生きていけない。自分の暮らしを自分でデザインしたい。そんな思いが地域創生への関心を育てたのだと思います。故郷の上勝町のための活動を考えていた妻を支えたいという気持ちも、もちろんありました。そこへ起きたのが2011年の東日本大震災です。同世代が次々と行動を起こすのを見て、「自分も」と決心しました。
- ──
- けれど、ご自身にはゆかりのない町です。どのようにモチベーションを育てたのですか。
- 松本
- 移住した頃、上勝町で開かれた、景観を考えるセミナーに参加しました。終了後、あるおじいさんが「家の前の花壇が荒れているから、明日からきれいにしよう」とおっしゃった。自分の当たり前の暮らしに手をかけて守っていこうとする人たちがいる。何歳になっても未来を考えて行動できる人がいることに、大きな勇気をもらいました。それが私にとって上勝町での原体験になり、この町に息づくマインドを大切にしていきたいと思わせてくれました。当時既に上勝町はゴミゼロ政策や「葉っぱ(つまもの)ビジネス」などで注目を集めていたので、世界から人が訪れる町になっていました。地域に寛容性が生まれていたことも、私のような移住者の活動の助けになったと思います。
- ──
- 移住2年後に、ご夫妻で素敵なカフェを地元にオープンされました。
- 松本
- 「上勝町を五感で感じる」がコンセプトでした。その頃から、他にもカフェやイタリアンレストラン、廃材を使ったビール工場などが同時多発的に生まれていきました。この動きが波になり、さらに大きな渦としていけるよう、貢献できればと思っています。
- ──
- 今年4月からは徳島大学にお勤めです。お仕事について教えてください。
- 松本
- 上勝でできたこともあるし、上勝だけではできなかったこともあります。そこでもっと活動の幅を広げて勉強したくなり、徳島大学・人と地域共創センターのコーディネーター・特別助教に応募しました。現在は地域の活性化を実践的に進めています。目立った事業としては、これは私の着任以前から続いている取り組みですが、徳島大学のキャンパスでファーマーズマーケットを地域の方と共に運営したり、小松島市の街づくりプロジェクト「こまつしまリビングラボ」に加わったり。よくある一過性のイベント作りではなく、住民や自治体、企業など地域の多様なプレイヤーを巻き込み、継続して地域の未来を共に築いていくプロジェクト作りができるように、意識しています。
地域創生のカギは危機感の共有と住民参画

- ──
- 地域創生がうまく進んでいる町と、そうでない町があると思います。差は何だとお考えですか。
- 松本
- 危機感を本当に感じているかどうかの違いかなと思います。上勝町がゴミゼロ政策を本気で推進したのは、切羽詰まったからでした。町が焼却炉を2基購入した直後、2000年にダイオキシン類対策特別措置法が施行され、排ガス基準をクリアできなくて使えなくなった。もう新しい焼却炉を買うお金はありません。だからゴミを減らすしかなかったのです。葉っぱビジネスも、主力作物だったミカンが台風で大打撃を受けたことが始まりでした。今では年収が一千万円を超える高齢者もおられます。お歳を召しても皆さん忙しく、こちらが元気をもらってばかりです。
- ──
- そこまで危機感が共有されていない地域では、何が成功へのカギですか。
- 松本
- よく「課題解決型ビジネス」と呼ばれますが、「課題解決」と言っているうちは「やらされている感」があると思います。それだけで自発的に動く人は限られている。そこに「楽しくできる」要素が加わるといいですよね。さらに言えば、そんなことをしなくても回っていける仕組みづくりが一番重要でしょう。
- ──
- 一人ひとりが加わることが大切。
- 松本
- つい先日、研修でアメリカのポートランドに行きました。全米で「住みたい街ナンバーワン」に選ばれた都市です。現地では当局が住民の意見も丹念にすくいながら、街のビジョンを1年半かけてじっくり作ったそうです。そうすれば後で市長や役人が交代しても簡単には覆せません。日本ではなかなか難しい手法ですが、非常に勉強になりました。
- ──
- 町づくりで大切にされていることは何ですか。
- 松本
- コーディネーターという役は、よくファシリテーションで終わってしまう場合が多いです。私はそれだけでなく、自分も実行主体の一員として関わっていきたい。そして人とのつながりを大切にしながら、未来のことを共に考えたい。他大学では、私と同じような役割に「連携」コーディネーターという名前がついていることが多いですが、徳島大学は「共創」コーディネーターです。これは、つながるだけではなく、共に何を創るかに重きを置いているという大学の強い想いがあります。
- ──
- 未来につながる、新しい志は育ちましたか。
- 松本
- 小さな町では、実現の難しいことは確かに多いです。でも、できない理由を考えて心配するよりも、未来につながることを考えて行動したいものです。たとえばゴミゼロ政策において、上勝町のリサイクル率は約80%にまで向上しています。しかし残りの20%はおむつなど、どうしても分別の困難な物です。この20%をゼロにするため、上勝からどんな仲間を作り、世界へムーブメントを起こしていけるかというやり甲斐が生まれています。今は立場上いったんカフェなどの運営から離れていますが、今後もあまり枠にはまるつもりはありません。移住して8年が経ちました、上勝というバックグラウンドが私を生かしてくれている。恩返しと言っては恥ずかしいですが、私にできることをしていきたいと思います。
(2019年8月19日、徳島市にて)
目次
第148号|2019.10
| 新島襄の言葉 | ||
|---|---|---|
| ……信仰を以て学校の基礎となし、学術を以て左右の翼と為し弥(いよいよ)振ひ、弥勉め、生徒諸君之主基督の為又邦家為御尽力あらん事を日夜祈居候…… 「1884年10月31日 新島八重宛て書簡」/ 「新島襄全集3」p305/柏木義円写 |
表紙裏 | |
| グラビア | |
|---|---|
| 法人 | 『一貫教育探求センター始動』 |
| 大学 | 『宇宙生体医工学研究プロジェクト キックオフシンポジウムを開催!』 |
| 女子大学 | 『食物栄養科学科科目「京の料理と菓子」に留学生が参加』 |
| 中学校・高等学校 | 『高校生徒会』 |
| 香里中学校・高等学校 | 2019年度 春のオープンキャンパス |
| 女子中学校・高等学校 | 『遠足』 |
| 国際中学校・高等学校 | 『高校球技大会』『日本文化の日』 |
| 小学校 | 『避難訓練』 |
| 国際学院 | 国際部:『Field Trip to Toyooka City』 初等部:『4年生宿泊学習 ~美山・宮津~』 |
| 幼稚園 | 『校祖墓参』『七夕発表会』 |
| 私の志 | ||
|---|---|---|
| 知って欲しいことを視聴者の目線で伝えたい。 | やさしいニュースを体現 川北円佳さん |
4 |
| 自分の暮らしを自分で創る。上勝町から世界への挑戦。 | 地域の力をつないで生かす 松本卓也さん |
6 |
| 特集 | ||
|---|---|---|
| 座談会 同志社一貫教育探求センター始動 |
圓月勝博/戸田光宣/石川博三/千田二郎 | 8 |
| シンポジウム 同志社の一貫教育に想うこと | 17 | |
| レクチャー | ||
|---|---|---|
| 宇宙生体医工学研究プロジェクト キックオフシンポジウム 「新時代を切り拓く、宇宙への挑戦〝Space-DREAM Project〞」 |
22 | |
| 建物案内 | ||
|---|---|---|
| 医心館(同志社大学) | 29 | |
| 南体育館(同志社中学校・高等学校 ) | 30 | |
| 同志社の逸品 | ||
|---|---|---|
| ギュツラフ訳聖書『約翰福音之傳』 | 同志社社史資料センター | 31 |
| 同志社ナウ | ||
|---|---|---|
| オープンキャンパス2019開催 | 大学入学センター | 33 |
| 「ガーデニングボランティア」 | 小﨑 眞 | 34 |
| 「数学甲子園」にチャレンジしました! | 園田 毅 | 35 |
| 緊急地震速報受信システムの設置 〜高校生徒自治会からの提案〜 |
加藤 憲 | 36 |
| 写真クラブの歴史と活躍 | 古谷 直子 | 37 |
| 私の研究・私の授業 | ||
|---|---|---|
| キャリアのけもの道 | 浦坂 純子 | 38 |
| 子育てへの不安が生んだ研究 | 荒渡 良 | 40 |
| デジタル・ヒューマニティーズの潮流 | 河瀬 彰宏 | 42 |
| 非行・犯罪行動変化と回復を支える | 毛利 真弓 | 44 |
| 英語のアポロジー(謝罪)についての研究と教育 | 北尾 キャスリーン | 46 |
| ホンモノから学ぶ社会科の学習 | 金山 香織 | 48 |
| 同志社クローズ・アップ | ||
|---|---|---|
| 世界で活躍できる人材を育てる法学部の授業 ―「グローバルな法律実務家」の育成を目指して |
川嶋 四郎 | 50 |
| 学部横断型PBL科目「プロジェクト科目」成果報告会を開催 | 大学今出川校地教務課 | 52 |
| ワンダフル・エイジング | 日下菜穂子 | 54 |
| 美術鑑賞授業の実践 「生活の中のデザイン〜色々な椅子〜」 |
塩田 侑佳 | 56 |
| 理科系クラブ研究発表会 | 古本 大 | 58 |
| スキー学舎 | 平岡 隆一 | 60 |
| SCHOLARS OF THE WORLD, UNITE! | Simon GODDARD WEEDON | 63 |
| 特別寄稿 | ||
|---|---|---|
| 前川道介氏の「言葉」 | 澤田 瞳子 | 64 |
| 新刊紹介 | ||
|---|---|---|
| 新島襄の教え子たち(ジャンル別) | 本井康博著 | 66 |
| 「通貨」の正体 | 浜矩子著 | 66 |
| 信託法をひもとく | 佐久間毅著 | 67 |
| 現代韓国を生きる若者の自立と親子の戦略 ―文化と経済の中の親子関係― |
ユンジンヒ著 | 67 |
| 詩画制作論の系譜 | 伊達立晶著 | 68 |
| 大統領とハリウッド―アメリカ政治と映画の百年― | 村田晃嗣著 | 68 |
| アベノミクスの成否 | 佐竹光彦他編著・北坂真一・川口章・三好博昭他著 | 69 |
| グローバル研究開発人材の育成とマネジメント ―知識移転とイノベーションの分析― |
宮本大他著 | 69 |
| ハーモニー探究の歴史―思想としての和声理論― | 大愛崇晴他著 | 70 |
| 50年目の「大学解体」20年後の大学再生 ―高等教育政策をめぐる知の貧困を越えて― |
佐藤郁哉編・他著 | 70 |
| 近代日本のメディア議員 ―「政治のメディア化」の歴史社会学― |
河崎吉紀他編著 | 71 |
| サイレント・マジョリティとは誰か ―フィールドから学ぶ地域社会学― |
轡田竜蔵他著 | 71 |
| 朝鮮半島 危機から対話へ ―変動する東アジアの地政図― |
太田修他著 | 72 |
| いま、教育と教育学を問い直す ―教育哲学は何を究明し、何を展望するか― |
小野文生他著 | 72 |
| 芥川龍之介選 英米怪異・幻想譚 | 藤井光他訳 | 73 |
| 認知症と医療 | 日下菜穂子他著 | 73 |
| お知らせ | ||
|---|---|---|
| 同志社大学古本募金 同志社女子大学DWCLA古本募金 ご協力のお願い | 74 | |
| ハリス理化学館同志社ギャラリー展示ご案内 | 75 | |
| 新島旧邸公開のお知らせ | 76 | |
| 同志社女子大学史料センター第24回企画展 同志社女子教育と体育・スポーツ | 77 | |
| 編集後記 | 78 |
|---|
| お問い合わせ |
同志社大学 広報課 TEL:075-251-3120 |
|---|
| 最新号 講読お申し込み・ご意見ご感想 バックナンバー一覧 |